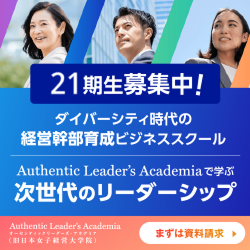アンガーマネジメントとは?怒りをコントロールするやり方・診断・研修などについて解説
- 2025年10月1日
- 読了時間: 13分
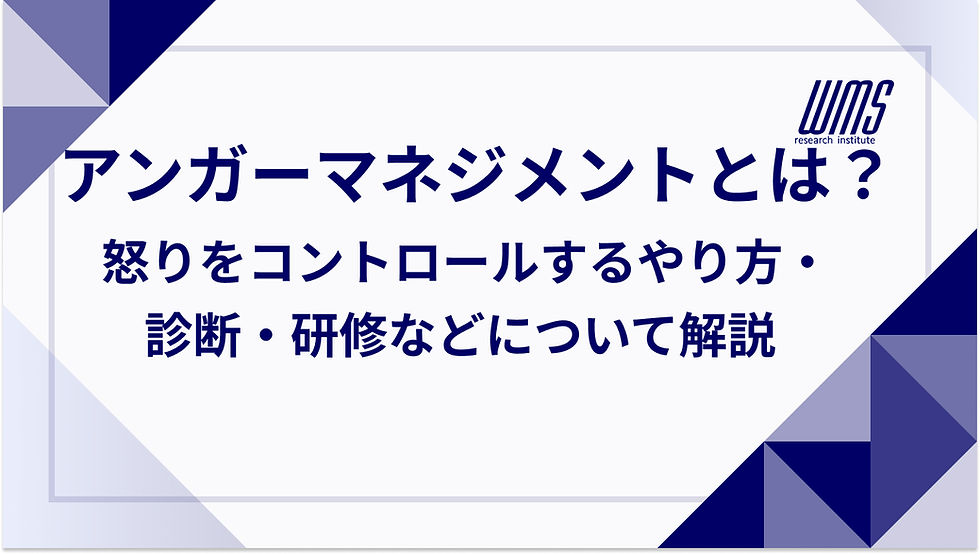
アンガーマネジメントとは、簡単にいえば「自分自身の怒りをコントロールするスキル」です。
介護や子育ての現場で重要視されてきたアンガーマネジメントですが、最近では、業種にかかわらず多くの企業がマネジメントや管理職の研修メニューにアンガーマネジメントを取り入れています。
本コラムでは、アンガーマネジメントが職場で求められている理由や実践的なやり方、企業での研修方法などについて解説します。
【 目 次 】
アンガーマネジメントの意味と定義
怒りが生まれる仕組み ~一次感情と「べき思考」~
職場で求められる理由
パワハラ防止につながる
職場の人間関係とコミュニケーションが改善する
社員のメンタルヘルスが向上する
怒りを6秒でやり過ごす「6秒ルール」とは
3つの代表的なやり方(呼吸法・怒りの記録・言葉の切り替え)
日常生活でできるアンガーマネジメントの工夫
アンガーマネジメント研修が注目されている理由
アンガーマネジメント研修で身につくスキルと効果
アンガーマネジメント研修の内容
【まとめ】アンガーマネジメントを組織で戦略的に活用する

アンガーマネジメントとは?基本の考え方と必要性
アンガーマネジメントとは、怒りの感情を適切に理解し、コントロールするための心理的スキルです。単に「怒らないようにする」ことではなく、衝動的な反応を抑えつつ、自分や相手にとって建設的な表現に変えることを目的とします。
はじめに、アンガーマネジメントの基本的な考え方と職場で求められている背景について解説します。
アンガーマネジメントの意味と定義
アンガーマネジメントとは、「怒りの感情を理解し、コントロールする方法論」のことです。
日本人は「アンガーマネジメント=怒らないようにすること」と考えがちですが、それは間違いです。重要なのは怒りを無理に抑え込むのではなく、適切に扱い、業務上のコミュニケーションを円滑にする点にあります。
特にビジネスの場では、顧客や上司、同僚との意見の相違が避けられません。怒りを感じること自体は間違ったことではありませんし、どちらか一方が無理にため込んでしまってはストレスの原因となります。むしろ、そこで感情に流されず、冷静に自分の考えを伝えられるかどうかが重要なのです。
アンガーマネジメントは、社員一人ひとりが建設的に意見交換をおこない、組織のパフォーマンスを高めるための基盤となるスキルといえるでしょう。
※参考:『アンガーマネジメント超入門 「怒り」が消える心のトレーニング』安藤俊介
(Discover21社 2021/10)
怒りが生まれる仕組み ~一次感情と「べき思考」~
アンガーマネジメントを実践するにあたっては、まず怒りが生まれる仕組みを理解しておくことが大切です。
有名なアドラー心理学では、感情を一次感情と二次感情に分け、自然発生的な一次感情を適切に表現できない場合に二次感情が発生するとしています。
一次感情 | 自然発生的な感情 | 「疲労感」「焦り」「心配」「不安」「落胆」 |
二次感情 | 一次感情がうまく処理されない場合に起こる感情 | 「怒り」 |
たとえば、締切に間に合わないかもしれないという焦りや、顧客からの厳しい要求による不安といった一次感情が怒りという二次感情を引き起こすわけです。
多くの場合、怒りは二次感情として発生するため、一次感情が何かを理解し見極めることが必要です。
怒りは、たとえば「部下は指示通りに動くべき」「顧客は感謝すべき」といった強い思い込み(べき思考)が裏切られたときに生じやすくなります。こうした“べき”が強すぎると、現実とのギャップに対して怒りの感情が生まれやすくなるのです。
「べき思考」は、個人の価値観や思想によって大きく異なりますので、年代や属性が多様化した職場ほど、衝突が起きやすくなります。
つまり、怒りの裏には隠された一次感情や価値観の衝突があるのです。こうした怒りの仕組みを理解することで、表面的な感情に振り回されず、冷静な問題解決や建設的な交渉に結びつけられるようになります。
職場で求められる理由
職場におけるアンガーマネジメントの必要性は年々高まっています。背景には、多様化する働き方や価値観、そしてハラスメント防止への社会的要請などがあります。
怒りをうまく扱えないと、パワハラや人間関係の悪化につながり、組織の信頼性や生産性を大きく損ないます。
さらに、パワハラを防ぐだけでなく、感情を冷静にコントロールできる人材は、リーダーシップを発揮しやすく、チーム全体のパフォーマンスを引き上げる存在となります。
そのため、多くの企業でアンガーマネジメントが注目され、管理職を中心に研修を導入するなどして、スキル習得を重視しているのです。
アンガーマネジメントの効果とメリット

アンガーマネジメントを導入することで、企業は職場環境の改善やリスクマネジメントの強化を実現できます。
感情のコントロールは個人のストレス軽減にとどまらず、組織全体の生産性や信頼性を高める要素です。特にビジネスの現場では、怒りが原因で発生するパワハラや人間関係の悪化が深刻な問題となるため、その予防に役立つ点は大きなメリットといえます。
また、社員のメンタルヘルスを守ることは、離職防止や企業価値の向上にも直結します。
ここでは主な3つの効果を解説します。
1. パワハラ防止につながる
怒りに任せた発言や行動は、パワハラやモラハラといったハラスメントの温床となります。
アンガーマネジメントを実践することで、上司が部下に対して感情的な指導を避け、冷静で建設的なフィードバックをおこなえるようになるでしょう。
パワハラ防止は単なるコンプライアンス対応にとどまらず、健全な職場文化を形成する基盤であり、企業のブランド価値向上にもつながります。
2. 職場の人間関係とコミュニケーションが改善する
ビジネスの現場では、多様な価値観を持つ社員同士が協力して業務を進める必要があります。しかし、感情的な衝突が繰り返されると信頼関係が損なわれ、チームのパフォーマンスが低下してしまうかもしれません。
アンガーマネジメントを学べば、社員は自分の怒りを客観的に把握し、適切な言葉で伝えられるようになります。その結果、相手を尊重しながら意見交換でき、チームワーク強化や組織全体のコミュニケーション活性化などの効果が期待できます。
3. 社員のメンタルヘルスが向上する
怒りを抑え込んだり爆発させたりすることは、社員の精神的・身体的負担につながります。慢性的なストレスは不眠や集中力低下、ひいてはメンタル不調や休職につながるリスクがあります。
アンガーマネジメントを通じて感情を健全に処理できるようになると、ストレス耐性が高まり、日常業務にも安定した姿勢で臨めます。
社員のメンタルヘルスが守られることは、組織の持続的成長や離職率の低下にも直結します。近年では「健康経営」の観点からも、企業が積極的に導入すべき取り組みのひとつといえるでしょう。
アンガーマネジメントのやり方・実践テクニック
アンガーマネジメントは知識として理解するだけでなく、日常生活のなかで実践することが重要です。
特に有名な「6秒ルール」をはじめ、呼吸法や怒りの記録、言葉の切り替えといった具体的なテクニックは、誰でもすぐに実践可能です。
こうした方法を習慣化することで、衝動的な行動を避け、建設的な人間関係を築くことにつながります。ここでは代表的なやり方を紹介します。
怒りを6秒でやり過ごす「6秒ルール」とは
怒りのピークは長くても6秒程度といわれています。瞬間的に怒りの感情が湧いても、6秒あれば次の理性が働いてくるわけです。
そこで、アンガーマネジメントでは、この6秒という短い時間をやり過ごし、衝動的かつ反射的な行動を抑える「6秒ルール」を推奨しています。
たとえば相手の発言に腹が立ったとき、深呼吸をしながら「6秒だけ待とう」と意識するのです。
たった6秒ですが、その間に怒りが少し落ち着くことで、言葉を選び直す余裕が生まれます。日常的に「まず6秒」と習慣化することは、最も簡単かつ効果的なアンガーマネジメントの基本テクニックといえるでしょう。
3つの代表的なやり方(呼吸法・怒りの記録・言葉の切り替え)
アンガーマネジメントには、誰でも取り入れやすい3つの代表的な方法があります。
呼吸法 | 怒りを感じたらゆっくり深呼吸する |
怒りの記録 (アンガーログ) | 怒りを記録して自分の怒りの傾向や原因を見える化する |
言葉の切り替え | 極端な表現や相手を責める言葉をやめて別の言葉に切り替える |
1つ目は「呼吸法」です。呼吸は感情のコントロールに重要な要素です。深呼吸をすれば自律神経が整い落ち着きを取り戻せます。6秒ルールでも、まずは呼吸を整えて時間をおくことを心がけましょう。
2つ目は「怒りの記録」です。怒りの記録をつけることをアンカーログといいます。いつ、どのような場面で怒ったのかを書きだすことで、自分の怒りの傾向や原因が見える化されます。自分の怒りを数値化して客観視するのも効果的です。
ただし、怒りが残っている状態でアンカーログを読み返すと感情が再現してしまう危険がありますので、ある程度時間を置いて気持ちが落ち着いてから振り返るようにしてください。
3つ目は「言葉の切り替え」です。「絶対」「いつも」といった極端な言葉を避け、「時々」「少し違う」と置き換えることで、感情のトーンを和らげられます。
また、「なぜ」「どうして」といった言葉には相手を責めるニュアンスがあるので、できるだけ使わないようにしてほかの表現に差し替える、といった対応も重要です。
日常生活でできるアンガーマネジメントの工夫
アンガーマネジメントは特別な場面だけでなく、日常生活のなかで少しずつ実践することが大切です。
たとえば、朝の通勤で混雑にイライラしそうなときは「自分では変えられない状況」と受け止め、音楽を聴くなど気持ちを切り替える方法が有効です。また、家族や同僚との会話では、相手の立場を意識して「なぜそう言ったのか」を考えると感情的な反応を防げます。さらに、十分な睡眠や適度な運動も怒りをため込まないために有効です。
生活習慣や考え方を工夫することで、自然とアンガーマネジメントを実践でき、長期的に安定した感情コントロール力を身につけられます。
アンガーマネジメント研修とは

アンガーマネジメント研修とは、怒りの感情を理解し、適切にコントロールするための知識やスキルを体系的に学ぶプログラムです。職場での感情的なトラブルやパワハラの防止、また社員のメンタルヘルスの向上を目的として導入されるケースが増えています。
最後に、アンガーマネジメント研修が注目されている理由や得られる効果、具体的な内容について解説します。
アンガーマネジメント研修が注目されている理由
近年、職場におけるハラスメント防止やストレスマネジメントの重要性が高まり、アンガーマネジメント研修への関心が急速に広がっています。
背景には、2020年以降に施行されたパワハラ防止法や、多様化する働き方のなかで増える人間関係の摩擦があります。
厚生労働省が2017年に立ち上げた「「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」では、パワハラを防ぐためのマネジメント方法について「一般社団法人日本アンガーマネジメント協会」からのプレゼンテーションが実施されました。※
そのため、感情コントロールの基本を全社員に学ばせ、職場の安心感や生産性を高める取り組みとして研修が注目されているのです。
アンガーマネジメント研修で身につくスキルと効果
研修を受けることで得られる最大の効果は「感情を客観的に捉える力」が高まることです。
怒りの原因や自分の反応パターンを理解することで、衝動的な言動を抑え、冷静に対応できるようになります。
具体的には、呼吸法や6秒ルールなどの実践スキルを習得し、状況に応じて使い分けられるようになります。さらに、研修を通じて相手の立場を理解する姿勢も養われるため、コミュニケーションの質が改善し、チームワークや信頼関係の強化にもつながります。
アンガーマネジメント研修の内容
アンガーマネジメント研修の内容の例をあげてみましょう。
怒りが生じる仕組み、メカニズムの理解
自分自身の怒りのタイプやトリガーの分析
6秒ルールの実践
アンガーログの記録方法と分析法
呼吸法やグラウンディングの実践
アンガーマネジメント研修では、まず心理学的な怒りが生じる仕組みを理解したうえで、自分自身の怒りのタイプやトリガーを分析します。
そのうえで、6秒ルールやアンガーログの記録、呼吸法や怒りから目をそらすグラウンディングなど、感情をコントロールする実践的な方法を習得するのが一般的です。
グループワークを通じて他者の価値観を理解し、相手に怒りをぶつけるのではなくリクエストを返すなどして、建設的なコミュニケーションを練習するプログラムも効果的です。
こうした多面的な学習により、理論と実践の両面から効果的に感情コントロール力を高められます。
アンガーマネジメント診断とは

アンガーマネジメント診断とは、自分や相手の怒りのタイプや傾向を客観的に把握できる診断テストのことです。
たとえば、日本アンガーマネジメント協会では、無料のアンガーマネジメント診断を公開しており、6つの動物キャラクターで怒りの傾向とタイプを分類しています。※
タイプ | 特徴 |
熱血柴犬 | 正義感が強い |
白黒パンダ | 何事にも白黒つけたがる |
俺様ライオン | プライドが高い |
頑固ヒツジ | 頑固で人の意見を聞かない |
慎重ウサギ | 慎重に考えたい |
自由ネコ | とにかく行動したい |
たとえば、正義感が強いタイプは、道徳や倫理、マナーなどに敏感で、組織の規律を重んじます。相手がこのタイプの場合は、まずは相手の言い分をよく聞く姿勢を示し、事実と思い込みの部分を分け対応することが大切です。
自分がこのタイプにあてはまる人は、価値観や倫理観は人によって異なることを理解し、押しつけないように配慮する必要があります。
こうした診断は数分程度ででき、手軽にセルフチェックが可能です。重要なのは「怒りの有無」ではなく「どういう状況で、どのくらい反応しやすいのか」を知ることです。
診断を通じて自分の弱点や相手の怒りの特徴・理由を理解することが、適切なアンガーマネジメントの第一歩となります。
『「怒り」を上手にコントロールする技術 アンガーマネジメント実践講座』日本アンガーマネジメント協会代表理事 安藤俊介(PHPビジネス新書)
【まとめ】アンガーマネジメントを組織で戦略的に活用する
アンガーマネジメントは、単に個人の感情を抑える技術ではなく、職場全体の生産性や健全な組織運営を支える戦略的なスキルです。
現代の企業は、社員の健康経営やハラスメント防止、エンゲージメント向上など多角的な観点からアンガーマネジメントに注目しています。企業がアンガーマネジメントを導入することは、単なる個人スキル向上にとどまらず、組織全体の持続的な成長と企業価値向上に直結する取り組みといえるでしょう。