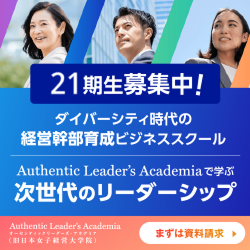ストレスマネジメントとは?意味・具体例・研修方法まで解説
- saganmm
- 2025年5月26日
- 読了時間: 11分

ストレスマネジメントとは、ストレスと上手につきあい対処することです。
ストレスマネジメントは心理学や医療介護分野で生まれた考え方ですが、近年ではビジネスや企業においても注目されています。
本コラムでは、ストレスマネジメントの意味と実践方法や企業における施策、研修の具体例などを解説します。
【 目 次 】
ストレスマネジメントの定義
心理学や医療介護分野におけるストレスマネジメント
ビジネスでストレスマネジメントが注目されている背景
セルフモニタリング(自分の状態を知る)
ストレスコーピング(具体的な対処法)
呼吸法・運動・趣味など日常的なケアの例
導入前の現状把握と課題の明確化
ストレスマネジメント研修の進め方とポイント
継続的な教育とフォローアップ
厚生労働省のストレスチェック制度とは?
厚生労働省が提供する簡易ストレスセルフチェック
ストレスマネジメントスコアとは?
ストレスマネジメントとは?意味と注目されている背景

ストレスマネジメントとは、ストレスと上手に向き合い、心身の健康を保つための考え方や実践方法を指します。
働き方の多様化や人間関係の複雑化により、ストレスの影響が問題視される現代において、個人のセルフケアだけでなく、組織としての対応も求められるようになりました。
本コラムでは、ストレスマネジメントの定義や医療・ビジネス分野での必要性について詳しく解説します。
ストレスマネジメントの定義
「ストレスマネジメント」とは、ストレスを自覚し、その影響を軽減・予防するための対処法や考え方を指します。
厚生労働省の運営するメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、ストレスマネジメントを以下のように定義しています。
ストレッサーを取り除いたり、ストレスを大きくしないための工夫や、ストレスによって生じている緊張状態やストレス反応の緩和など、ストレス生成のあらゆるプロセスに包括的に働きかけることを言います。 引用元:こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト|ストレスマネジメント:用語解説
「ストレッサー」とは、ストレスの原因となる刺激や状況のことです。
心理学や医療介護分野におけるストレスマネジメント
心理学や医療・介護の現場では、ストレスマネジメントはまずは臨床現場での対処療法として実施されてきました。近年では、問題を抱えている者への対処療法としてだけではなく、ストレスへの対処力を高めることを意図した予防的ストレスマネジメントが求められています。
医療介護の現場では、患者や利用者への対応は身体だけでなく、精神的なサポートも必要とされ、関わる職員自身もストレスの影響を受けやすいという特徴があるからです。
予防的ストレスマネジメントの例としては、認知行動療法を取り入れたストレス対処や、職員向けのメンタルヘルス研修などが挙げられます。
こうした取り組みは、介護の質を保ち、職員のバーンアウト(燃え尽き)を防ぐためにも重要です。人と深く関わる現場では、特にストレスマネジメントの重要性が高まっています。
ビジネスでストレスマネジメントが注目されている背景
ビジネスの現場では、ストレスによるメンタル不調や離職が課題となっており、対策としてストレスマネジメントが注目されています。
厚生労働省の調査では、過去1年間にメンタルヘルスの不調により連続1カ月以上休職した労働者がいる事業所の割合は、全体では13.5%です。従業員1,000人以上の規模の企業では91.2%、従業員100~299人規模の企業でも55.3%と高い数値が出ています。
メンタルヘルス対策に取り組んでいる企業の割合は63.8%で、多くの企業がストレスチェック制度やメンタルヘルス研修などの対策を導入しています。※
職場の生産性や人材の定着率を向上させるためにも、いまやストレスマネジメントは企業戦略の一環としても重視されているのです。
ストレスマネジメントの具体例と実践方法

日常的に行えるストレスマネジメントを習慣化することで、ストレスによる心身への悪影響を防ぎやすくなります。ここでは、自分自身の状態を把握し、適切に対処する方法を具体的に紹介します。
セルフモニタリング(自分の状態を知る)
「セルフモニタリング」とは、日々の感情や体調の変化を記録し、ストレスの原因や傾向を分析する方法です。
ストレス対策の第一歩は、自分の心と身体の状態を正しく把握することです。 いまの自分にどれくらいストレスがかかっているのか?に気づいていなければ、対処やケアの方法を考えることもできません。
ストレスに気づくためには、日頃から自分の心身の状態を観察したりチェックしたりする習慣をつけます。
たとえば、気分が落ち込んだ日には「何があったか」「どう感じたか」「どのような身体の反応が出たか」を書き出します。こうすることで、自分がどのような状況にストレスを感じやすいかが明確になり、対策を立てやすくなります。
ストレスコーピング(具体的な対処法)
ストレスを感じた際に行う具体的な対処法を「ストレスコーピング」と呼び、たとえば以下のような方法があります。
|
たとえば、「上司から理不尽に叱責された」という場面を想定した場合、それぞれのコーピングスタイルによって次のような対処が考えられます。
問題焦点型コーピング
原因を分析し、具体的な改善行動をとります。たとえば、上司に話をして誤解を解く、業務内容を見直して再発防止策を講じるなどです。
情動焦点型コーピング
ストレスに対する感情の受け止め方を変えます。たとえば、「自分を成長させるためのフィードバックだったかもしれない」と捉え直すなど、発想の転換で気持ちを落ち着かせます。
社会的支援探索型コーピング
同僚や友人、家族に相談し、共感や助言を得て心理的な安心感を得ようとします。「つらかったね」と話を聞いてもらうことだけでも、大きな支えになります。
気晴らし型コーピング
一時的にストレスから離れることでリフレッシュを図ります。たとえば、運動や音楽、趣味に没頭して気分を切り替え、冷静さを取り戻すなどです。
ストレスコーピングはどれが正しいということはなく、自分に合う方法を複数持つことが大切です。状況に応じて適切に使い分けるようにしましょう。
呼吸法・運動・趣味など日常的なケアの例
日常生活のなかで継続的に行えるストレスケアも、ストレスマネジメントには欠かせません。 日常生活のストレスケアとしては、たとえば以下のようなものが挙げられます。
|
たとえば、深呼吸や腹式呼吸は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせます。
また、入浴や散歩は気分転換やリラクゼーションに効果的です。さらに、読書や音楽、アートなどの趣味に時間を使うことも、情動の安定に役立ちます。
これらの習慣を持つことで、ストレスを溜め込みにくい生活スタイルが築けます。自分に合った方法を見つけ、日々のなかで実践することが重要です。
企業におけるストレスマネジメントの導入と研修

企業が従業員の健康を守るためにストレスマネジメントを導入することは、生産性向上や離職防止にもつながります。
ここでは、導入にあたっての現状把握、研修の進め方、そして組織としてのサポート体制について解説します。
導入前の現状把握と課題の明確化
ストレスマネジメントを導入するには、まず職場の現状を把握し、どのような課題があるかを明確にすることが重要です。
なぜなら、職場ごとにストレスの原因や影響が異なるからです。
たとえば、業務過多による疲労、上司との関係による心理的負担など、原因を特定しないまま対策を講じても効果は薄くなります。ストレスチェックや従業員アンケートを活用し、具体的な課題を可視化することが大切です。
現状を正しく理解したうえで、以下のような施策を職場ごとに導入するか決めていきましょう。
|
管理職や特定の職層に向けて、ストレスマネジメント研修を実施するのもおすすめです。ストレスマネジメント研修の進め方については次でくわしく解説します。
ストレスマネジメント研修の進め方とポイント
ストレスマネジメント研修とは、ストレスマネジメントについて正しい知識と対処法を学ぶ研修です。
ストレスマネジメント研修では、外部講師などを招いて以下のような内容を学習します。
・ストレスとは何か ・ストレス要因の分析法 ・ストレス解消への対処法 ・ポジティブシンキングについて |
ストレスマネジメント研修でポイントとなるのは、座学だけでなくワーク形式を取り入れることです。受講者が自分自身のストレス状態を振り返るワークや、呼吸法・認知の切り替えといった実践的なスキルの習得を通じて、知識が定着しやすくなります。
また、管理職には部下の変化に気づくための視点や声のかけ方も研修に含めると、職場全体のメンタルヘルス対策が強化されるでしょう。
継続的な教育とフォローアップ
ストレスマネジメントの効果を継続的に発揮させるには、継続的な教育とフォローアップが欠かせません。
ストレスマネジメントは、企業が一方的に施策を提供するだけでなく、従業員自身に適切な知識やマインドを見につけてもらう必要があります。そのため、情報提供や研修などは継続的におこなうことが大切です。さらに、施策や研修を実施した後では、必ず効果の検証とフォローアップをおこなうようにしましょう。
ストレスマネジメントのセルフチェック方法

ストレスと上手に付き合うためには、まず自分の状態に気づくことが大切です。その第一歩として有効なのが、セルフチェックの活用です。
最後に、厚生労働省のストレスチェック制度やセルフチェックを紹介しますのでお役立てください。
厚生労働省のストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法に基づき、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした仕組みです。
従業員が50人以上いる事業場では、年1回の実施が義務づけられています。
検査項目には、仕事の量や人間関係、心理的・身体的反応などが含まれ、質問票形式で行われます。制度の目的は、個人のストレス状況を把握し、必要に応じて産業医との面談や職場環境の改善につなげることです。
厚生労働省のサイトでは、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等が出来る「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料でダウンロードできます。
▼厚生労働省 ストレスチェックダウンロードはこちら
厚生労働省が提供する簡易ストレスセルフチェック
厚生労働省が提供する働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「5分でできる職場のストレスセルフチェック」が掲載されています。
4つのSTEPによる簡単な質問から、職場におけるストレスレベルを測定できますので、簡易的なセルフチェックに活用するとよいでしょう。
▼こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト|5分でできる職場のストレスセルフチェックはこちら
ストレスマネジメントスコアとは?
ストレスマネジメントスコアとは、個人がストレスにどう対処できているかを数値化した指標です。
主に民間の研修プログラムなどで活用されており、ストレスへの耐性や対応スキルのレベルを客観的に把握するために用いられます。
自己理解を深めるだけでなく、改善すべき行動や考え方を明確にするきっかけになります。点数の高低に一喜一憂するのではなく、自分なりの成長指標として活用することが大切です。
【まとめ】企業にもストレスマネジメントが求められている
ストレスマネジメントの意味や実践方法、企業における施策や研修導入のポイントなどを解説しました。
多くの企業が従業員のメンタル不調や離職を課題として抱えており、ストレスマネジメントへの注目が高まっています。
仕事をするうえでストレスをゼロにはできません。環境がますます多様化・複雑化するビジネスマンや企業側にとっては、ストレスの原因を断つのではなく、ストレスと上手に付き合い自分のメンタルヘルスをコントロールしていくストレスマネジメントが求められているのです。