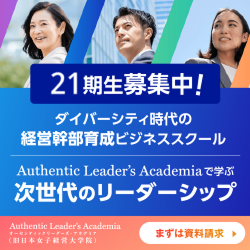コールセンター外注とは?費用・メリット・成功事例を解説
- なつき 高橋
- 2025年7月1日
- 読了時間: 11分

「コールセンター業務を外注したいけれど、委託会社の選定に悩んでいる」
「コールセンターを自前でやるかアウトソーシングするかどちらが良いかわからない」
コールセンター業務の外注や委託をする際には、費用対効果や目的に応じて検討する必要があります。
本コラムでは、コールセンター外注の基礎知識やメリット・デメリット、費用相場などについて解説します。
【 目 次 】
なぜ今、コールセンター外注が注目されているのか
自社運営(インハウス)との違いとは
コールセンター外注とオムニチャネル
【メリット】コスト削減・品質向上・人手不足解消
【デメリット】社内ノウハウの蓄積不足・情報管理リスク
月額固定制・従量課金制など料金モデルの違い
1コールあたりの単価の目安
コールセンター外注費用の比較ポイント
PrimeConectの導入事例紹介①
PrimeConectの導入事例紹介②
PrimeConectの導入事例紹介③
コールセンター外注とは?基本知識と導入背景

コールセンター業務の外注は、業務効率化やコスト削減を目的に、多くの企業で導入が進んでいます。
人材不足や業務の多様化に対応する手段として注目されており、従来の自社運営(インハウス)との違いや、オムニチャネル対応との関連も理解しておくことが重要です。
はじめに、外注化の基本知識とその導入背景についてわかりやすく解説します。
なぜ今、コールセンター外注が注目されているのか
近年、多くの企業がコールセンター業務を外部へ委託する「外注化」を進めています。
その背景には、人手不足や業務効率化の必要性、そして顧客対応品質の向上などが挙げられます。
外注化を活用すれば、専門スキルを持つスタッフに対応を任せることができ、自社の人材やリソースをコア業務に集中できます。
また、柔軟な人員体制や24時間対応なども実現しやすく、顧客満足度の向上にもつながります。
このように、業務効率・品質・コストのバランスを最適化する手段として、コールセンター外注を導入する企業が増えています。
自社運営(インハウス)との違いとは
コールセンターを自社で運営することを「インハウス」といいます。インハウス型とアウトソース型では、コールセンターの運営面で大きな違いがあります。
インハウスでは自社の社員が業務を担うため、ブランド理解が深く柔軟な対応が可能です。しかし、本業とはあまり関わりのない部分でリソースをとられたり、稼働状況や時期に応じて柔軟な対応がとりづらかったりすることがあります。
一方、外注では業務全体または一部を専門業者に委託することで、人件費や設備費を削減できます。
ただし、品質管理や情報共有の仕組みづくりが必要となるため、導入には委託する業務範囲やフローを明確にし、適切なシステムや外注先を選定することが重要です。
コールセンター外注とオムニチャネル
コールセンターにおける「オムニチャネル」とは、電話・メール・チャット・SNSなど、複数の顧客接点を一元的に管理し、シームレスに対応する仕組みのことを指します。
コールセンターのオムニチャネル対応が求められ、メール・チャット・SNSなど複数の窓口を一元管理する顧客対応が主流になりつつあります。こうした複雑な対応を効率よく行うには、マルチチャネル対応の実績を持つ外注業者の活用が効果的です。
各チャネルの対応を分業化・最適化することで、迅速かつ一貫性のある顧客対応が実現でき、企業全体のCX(顧客体験)向上にも貢献します。
コールセンターを外注するメリットとデメリット

コールセンターを外注することで、コストや人員の課題を解決しやすくなる一方で、自社内にノウハウを蓄積しづらくなるのでは?といった懸念もあります。
外注化には多くの利点がありますが、その導入にあたっては慎重な判断と体制整備が欠かせません。
ここでは主なメリットとデメリットについて解説します。
【メリット】コスト削減・品質向上・人手不足解消
コールセンターを外注するメリットとしては、主に以下のような点が挙げられます。
運営コストの削減
対応品質の向上
人手不足の解消
コールセンターの人員を自社内で採用・教育・管理するには多くのコストと時間がかかりますが、外注すればその負担を軽減できます。
加えて、外注先は専門的なスキルを持つオペレーターや管理体制を整備しているため、高品質な顧客対応が可能です。
また、繁閑差に応じた柔軟な人員調整がしやすくなり、季節変動やキャンペーン時の業務増加にもスムーズに対応できる点もメリットといえます。
特に近年は労働人口の減少が進んでおり、自社内での人材確保が難しいなかで、外注化は有効な解決策の一つとなっています。
【デメリット】社内ノウハウの蓄積不足や情報管理のリスク
一方で、外注には注意すべきデメリットも存在します。
社内ノウハウの蓄積不足のリスク
情報管理不足のリスク
外注先に業務を任せきりにしてしまうと、顧客から寄せられた貴重な意見やクレーム対応の知見が、社内で十分に共有・活用されず、商品開発やサービス改善の機会を逃す恐れがあります。
実際には、委託先から日次・週次でレポートが提出されたり、自社の担当者が常駐したりと、情報共有の体制が整っているケースも多くありますが、それを社内でどう活かすかは運用次第です。
また、個人情報や取引情報といったセンシティブなデータを外部に預けることになるため、情報漏洩リスクやセキュリティの脆弱性にも留意が必要です。
これらのデメリットを最小限に抑えるためには、信頼できる委託先の選定と、情報共有体制の強化が不可欠です。外注先の信頼性や契約条件、管理体制を慎重に確認したうえで導入することが求められます。
コールセンター外注の費用相場と料金体系
コールセンターを外注する際の費用は、提供されるサービス内容や業者によって大きく異なります。
契約形態や課金方式、対応件数などが料金に影響するため、基本的な料金体系を理解することが重要です。
ここでは代表的な料金モデルと、その費用相場を紹介します。
参考:パーソルビジネスプロセスデザイン|コールセンターの費用はいくらかかる?外部委託する際の費用を徹底解説
月額固定制・従量課金制など料金モデルの違い
コールセンター外注には、月額固定制と従量課金制という2つの代表的な料金モデルがあります。
費用 | 仕組み | |
月額固定制 | 固定 | 一定のコール数までは固定で対応 |
従量課金制 | 変動 | 1コールあたりの単価を決め、対応件数に応じて課金 |
月額固定制は、毎月一定の費用で決められたコール数まで対応してもらえる方式なので、受電件数が安定している業務に向いています。
一方、従量課金制は対応件数に応じて課金される仕組みで、繁閑差が大きい業務や短期キャンペーンでの利用に適しています。
固定制と従量課金制を併用しているコールセンター・コンタクトセンター外注業者も多く、この場合は、月当たり決められた件数までは固定料金を払い、それを超過した分にだけ従量課金制が適用されます。
1コールあたりの単価の目安
外注先に支払う1コールあたりの単価は、業務の難易度や対応時間によって異なります。
大手コールセンター委託会社の1コールあたりの単価を比較した表は以下のとおりです。
大手委託会社A | 大手委託会社B | 大手委託会社C | |
固定制 | 95,000円 (~300件まで) | 15,000円 (~100件まで) | 10,000円 (~80件まで) |
従量課金制 | 300円/コール | 150円/コール | 200円/コール |
受付や一般的な問い合わせなどシンプルなインバウンド業務のコール単価は150~500円程度です。セールスなどのアウトバウンド業務、専門的な対応や英語などの多言語対応の必要がある場合などは、単価は高くなる傾向にあります。
さらに、業務フローの改善や顧客対応品質の向上を目的とした外注の場合には、人員の育成や専門のコンサルティングが必要となるため、1コールあたりの単価が高くなったり、別途費用が発生したりすることもあるので注意が必要です。
件数が多い場合はボリュームディスカウントが適用されることもあるため、外注する業務内容を明確にしたうえでボリューム予測を正確に見積もり、比較検討することが重要です。
コールセンター外注費用の比較ポイント
コールセンター外注の費用を比較する際は、単価だけでなく総合的な条件も確認すべきです。
コールセンターの外注先を選定する際には、まず外注する目的や優先順位を明確化したうえで、以下のような項目を総合的に勘案しましょう。
初期費用の有無
使用するシステム
サポート体制
人材教育体制
マニュアルや業務フロー作成対応の有無
1件あたりの対応時間
業務の対応範囲(24時間対応や多言語対応など)
トラブル時の対応方針
運用レポートの有無
単純な価格比較だけでなく、サービス内容とのバランスを重視することがポイントです。
コールセンター外注の成功事例

コールセンターの外注を行う目的は、応対品質の向上やオペレーション効率化など企業によってさまざまです。
コールセンター外注を活用し、顧客満足度やビジネス成果の向上などを実現した成功事例をご紹介します。
導入事例① 健康食品メーカーのケース
某健康食品メーカーのコンタクトセンターでは、解約阻止率目標の30%に対し10%未満と低迷し、応答率も80%台に留まっていました。
顧客の疑問や要望に答え解約阻止するためには、オペレーターはただ応対するだけでは足りず、製品や関連法規についての高度な知識が必要とされます。
外注先に相談したところ、オペレーターの教育強化とチームビルディング導入を提案されました。全体のスキル底上げと組織の活性化を図った結果、解約阻止率は10%から40%以上に向上し、応答率も95%以上を維持できるように改善されたのです。
さらに、作業の効率化によりオペレーターの稼働率は150%まで向上。スキルの高いオペレーターは、コンタクトセンターからインサイドセールスに転換する組織改変をおこない、アウトバウンドによる新たな売り上げを創出できました。
従業員のエンゲージメント向上と共に、コンタクトセンターはセールススキルを養う若手人材の育成機関へと進化しています。
導入事例② 大手ライフラインサービスのケース
某大手ライフラインサービスのカスタマーサポートではクレーム対応が多く、効率の悪いコストセンター化していました。
特に2次クレーム、3次クレームの比率が多く、結果的に訪問謝罪に発展するなど、深刻な状況に陥っていました。
思い切ってコールセンターの外注先に相談したところ、オペレーターに対して顧客の感情や背景を理解できるような対話トレーニングの実施を提案されました。
この対話トレーニングにより、オペレーターに高いホスピタリティと効果的なヒアリングスキルを身につけさせ、顧客との対話が改善されたのです。
さらに、音声・録音データの分析と評価やクレーム入電を案件レベルに選別化し、組織体系への見直しも実施。大幅な効率改善と顧客満足度アップを実現しています。
導入事例③ ITスタートアップ企業のケース
某ITスタートアップリリースでは、リリースしたIT製品に対し、顧客サポートのためのスタートアップ特有の迅速な開発に対応できるテクニカルサポートセンターの構築が必要でした。
しかし、サポートセンター構築経験や社内リソースがなく、ゼロからの運用設計はスタートアップ企業には大きな負担となります。
そこでコールセンターの運用設計を外注先に依頼。テクニカルサポートセンターのDX化を推進し、AIを活用したオペレーターのマルチ化を実現しました。
さらに、サービス毎にチーム編成し、それぞれの育成スキームを標準化することにより、オペレーションの属人化を抑制に成功。はじめは10名以下だったセンターが、DX化とチームのマルチ化により、100名規模の多機能センターへと拡大しました。
【まとめ】コールセンター外注は費用対効果と目的に応じて導入を
コールセンター業務委託の方法、外部委託のメリット・デメリットなどについて解説しました。
コールセンターの業務を委託する際には、業務の質・本業との相性や将来的な指針などを総合的に判断することが重要です。コスト面だけでなく、企業のサービス品質やブランドイメージ向上という観点からも検討する必要があります。
アイデンティティー・パートナーズが提供する「Prime Connect」では、長年の実績を持つ専門チームがコールセンターを運営します。オペレーターやSV・管理者など、現場第一線での経験を積んだ精鋭を揃え、安定したオペレーションと最短最速でのパフォーマンス提供が可能です。
質の高い顧客対応はもちろん、営業・販売支援からバックオフィス支援まで、お客様の状況や課題に合わせたコールセンター体制構築を支援いたしますので、ぜひ一度お問い合わせください。
▼最高の顧客体験を創出するリレーションパートナー「Prime Connect」はこちら