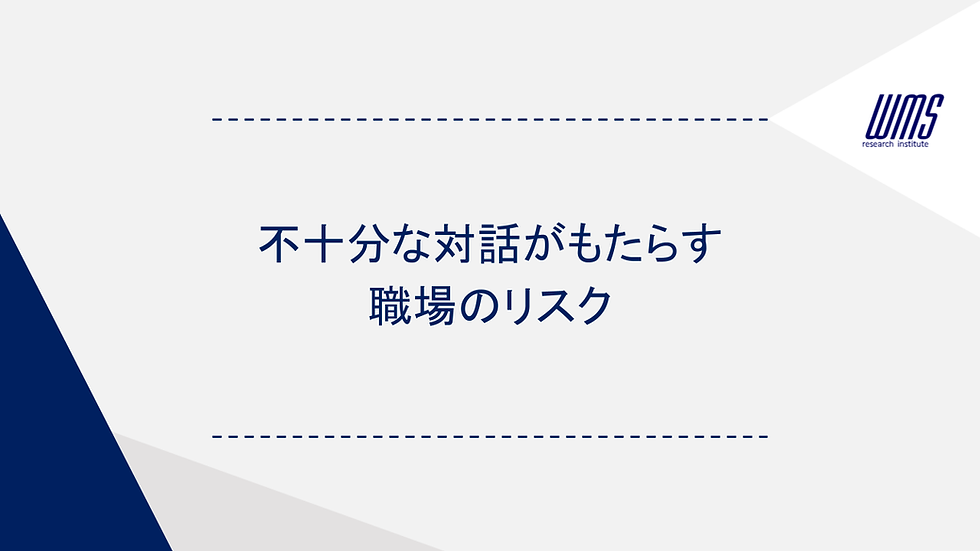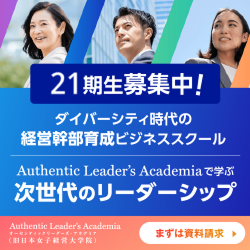職場の人間関係を改善する方法と対処法【割り切る・孤立しない・気にしないコツ】
- 2025年2月12日
- 読了時間: 13分

あなたの職場の人間関係は良いほうですか?それとも悪いほうですか?
働き方の多様化やコミュニケーション方法の変化などにより、職場の人間関係に悩む人が増えています。
そこで本記事では、職場の人間関係が業務に与える影響や、ストレスを感じる理由、改善する方法などを解説します。
職場の人間関係を気にしないコツや無料のストレスチェックなども紹介しますので、参考にしてください。
【 目 次 】
職場の人間関係に悩む人が増えている背景
職場の人間関係が業務に与える影響
職場の人間関係を割り切る?ドライになり過ぎると危険
性格の不一致や価値観の違い
過度な競争や上下関係のストレス
社員同士のコミュニケーション不足 パワハラ・モラハラ・嫌がらせ
必要以上に「気にしない」マインドセットを持つ
孤立を防ぐための自己分析と行動改善
ネガティブな関係や相手には深入りしない
ポジティブな「問い」を使って会話を円滑にする
トラブルを回避するための傾聴力と対話術
信頼関係を築くための言葉の選び方
職場の人間関係は割り切るのが大事?

日本労働調査組合の調査によると、職場の人間関係を良好と感じているのは全体の32.1%と決して多くありません。職場の人間関係を理由に退職、転職を検討したことがあるのは58.5%と過半数を超えており、多くの人が職場の人間関係に悩んでいることがわかります。※

日本労働調査組合のプレスリリース| 職場の人間関係が「良好」と感じているのは約3割「職場の人間関係に関するアンケート」結果発表 より
職場の人間関係では、ある程度の割り切りが必要、と考える人もいるようですが、コミュニケーション不足やドライ過ぎるのも問題です。
まずはじめに、職場の人間関係に悩む人が増えている背景、それが業務に与える影響などについて解説します。
※参考:日本労働調査組合のプレスリリース| 職場の人間関係が「良好」と感じているのは約3割「職場の人間関係に関するアンケート」結果発表
職場の人間関係に悩む人が増えている背景
近年、職場の人間関係に悩む人が増加しています。その背景には、働き方の多様化やコミュニケーションの変化、企業文化の影響など、さまざまな要因が関係しています。
2022~2023年に産業医や社外窓口相談に寄せられた相談内容を分析した統計では、新型コロナウイルスに関する相談は激減した一方で、メンタルヘルス、ハラスメントの相談は増加しました。
相談内容で最も多いのは「上司・先輩との関係」、増加率で一番高かったのは「同僚や部下との関係」です。
統計での分析結果では、LGBTQ、障害者雇用など、相談者属性の多様化が進んでいることも特徴として挙げられました。※
リモートワークやハイブリッドワークの普及により、同僚や上司との直接的な対話の機会が減少し、業務上の意思疎通が難しくなっているケースが増えています。
さらに、価値観の多様化も影響しています。異なる世代やバックグラウンドを持つ人が同じ職場で働くなかで、仕事に対する考え方やコミュニケーションのスタイルの違いが摩擦を生むことも少なくありません。
このような背景から、職場での人間関係に悩む人が増えているのです。
※参考:共同通信PRワイヤー| ドクタートラストのプレスリリース| 「上司や同僚・部下との人間関係」に悩む人が圧倒的に増加
職場の人間関係が業務に与える影響
職場の人間関係は業務上でも大きな影響を与えます。HR総研の社内コミュニケーションについてのアンケート調査では、「社員間のコミュニケーション不足は業務の障害になる」と答えた人が9割以上にのぼりました。
どのような業務において障害になるか、という質問では、「迅速な情報共有」「部署内のチームビルディング」「部門間・事業所間の連携」が多数を占めています。
職場の人間関係に問題があると、組織内の協力や連携がうまくいかず、業務の効率化や組織の生産性にマイナスとなります。また、問題が長期化すれば、メンバーのモチベーションやエンゲージメントにも悪影響を及ぼすでしょう。
※参考:ProFuture株式会社/HR総研
職場の人間関係を割り切る?ドライになり過ぎると危険
職場の人間関係に悩んだ際、「必要以上に関わらない」「仕事と割り切る」といったドライな考え方を持つ人もいます。確かに、感情的になりすぎず、冷静に対応することはストレスを減らすために有効です。
しかし、極端にドライになりすぎることにはリスクも伴います。完全に割り切ってドライになり過ぎると、職場での協力関係や情報共有に悪影響を及ぼすからです。
上で解説した通り、職場の人間関係が悪化することは、組織の運営や生産性に大きなマイナスになります。
あまりにドライな態度を取ると、周囲から「冷たい人」「協調性がない人」と見られてしまうリスクもあります。過度な割り切りは逆に働きづらさを生むこともあるので注意が必要でしょう。
職場の人間関係に悩んだときは、「適度な距離感」を意識することが大切です。ある程度割り切りながらも孤立しないように適度な距離を保つための方法、コミュニケーションスキルについてはのちほど詳しく解説します。
職場の人間関係を円滑にするためには、効果的なマネジメントが欠かせません。
マネジメントについて詳しく解説した記事も、ぜひご覧ください。
職場の人間関係でストレスを感じる理由

職場の人間関係でストレスを感じる原因は、性格や価値観の違い、競争や上下関係、コミュニケーション不足、そしてパワハラやモラハラなど、多岐にわたります。
それぞれの状況がストレスを生む背景を理解することで、対策を考える第一歩になります。
ここでは、いくつかの具体的な例を挙げて職場の人間関係でストレスを感じる理由をみていきましょう。
性格の不一致や価値観の違い
職場ではさまざまな性格や価値観を持つ人々が集まります。そのため、「考え方が合わない」「仕事への取り組み方が違う」といった理由から、ストレスを感じることがあります。たとえば、慎重派の人がスピード重視の同僚と一緒に仕事をする際、意見が対立しやすくなるかもしれません。
日常生活では性格や価値観が合わない人とは付き合わなければよいのですが、職場の人間関係ではそうもいきません。プライベートでは気にしなくてもいいような性格や価値観の違いでも、職場で毎日顔を合わせなければいけない状態が続けば、ストレスの要因となります。
過度な競争や上下関係のストレス
競争意識が強い職場では、社員同士がライバル意識を持ち、ギスギスした雰囲気になりがちです。
また、成果主義の職場では、評価を得るために同僚との衝突や孤立を招く場合があります。さらに、厳しい上下関係がある職場では、部下が上司の指示に無理に従い続けることで、大きな精神的負担を抱えることになるでしょう。
職場がこのような環境にある場合は、持続的なストレスにつながる恐れがあります。
社員同士のコミュニケーション不足
職場でのコミュニケーション不足も、職場の人間関係を悪化させる大きな要因となります。
先に引用したHR総研のアンケートでは、大企業を中心に「社内コミュニケーションを阻害している原因」として「対面コミュニケーションの減少」や「働き方の多様化」を挙げる割合が30~40%と高くなっています。
コロナ禍で急速に普及したテレワークやオンライン化、あるいは働き方の多様化などにより、社内コミュニケーションを対面で取りにくくなっているのです。※
物理的なコミュニケーションの時間や機会が減ることで、お互いの意図や考えを理解しにくくなり、信頼関係が損なわれるリスクもあります。こうした状況が続くと、職場の雰囲気は悪化し、ストレスの要因となるでしょう。
※参考:ProFuture株式会社/HR総研
パワハラ・モラハラ・嫌がらせ
上司や同僚によるパワハラやモラハラ、あるいは嫌がらせは、職場でのストレスの原因の一つです。
たとえば、上司からの理不尽な叱責や過度な要求、同僚からの陰口や無視といった行為が挙げられます。こうした行動は、被害者に大きな精神的苦痛を与え、最悪の場合には健康を損なう結果にもつながります。
これらの問題に直面した際には、早急に相談窓口や外部機関のサポートを求めることが重要です。
職場の人間関係を改善する方法【割り切る・孤立しないために】

職場での人間関係がストレスの原因になることは多いものです。ですが、その関係を改善するための具体的な方法を知っておくことで、気持ちが楽になり働きやすい環境をつくれます。
ここでは、職場の人間関係を改善するための3つのアプローチを紹介します。
「気にしない」マインドセットを持つ
職場での人間関係に悩む大きな原因の一つは「気にしすぎる」ことです。
相手の些細な反応や言葉に敏感になりすぎると、自分自身が疲れてしまいます。そこで大切なのが、「必要以上に気にしない」マインドセットを持つことです。マインドセットとは、心構えや考え方のフレームワークといった意味をもつ言葉です。
「相手の機嫌は自分の責任ではない」「全員に好かれる必要はない」と割り切ることで、不要なストレスを減らし、自分らしさを保てます。また、自分の価値観や目標に集中することで、周囲の些細なことに振り回されることが減るでしょう。
孤立を防ぐための自己分析と行動改善
職場での孤立は大きなストレス要因です。
孤立を防ぐためには、まず自己分析が欠かせません。「自分はどうして孤立しがちなのか」「周囲との関わり方に改善の余地はあるか」といった問いかけをしてみましょう。そして、必要であれば行動を改善することです。
たとえば、積極的に挨拶をしたり、ちょっとした雑談をしたりするだけでも、人との距離はぐっと縮まります。小さなことから行動を変えていくことで、職場での人間関係も少しずつ良好になっていくはずです。
ネガティブな関係や相手には深入りしない
どの職場にも、合わない人やネガティブなエネルギーを持った人はいるものです。そういった人との関係に深入りしてしまうと、自分まで引きずられてしまうことがあります。
そこで意識したいのは「適度な距離感を保つ」ことです。業務に支障が出ない程度に必要最低限の関わりに留め、感情的なやり取りは極力避けるようにしましょう。
また、信頼できる人との関係を大切にし、そこからエネルギーをもらうように心がけると、ネガティブな影響を受けにくくなります。
職場の人間関係を良好に保つためのスキル

職場での人間関係は、仕事の効率やメンタルヘルスに大きな影響を与えます。良好な関係を築くためには、日常のコミュニケーションを工夫し、相手との適切な距離感を保つことが重要です。
ここでは、良い職場の人間関係を保つために役立つ3つのスキルを紹介します。
ポジティブな「問い」を使って会話を円滑にする
職場での会話がスムーズに進むかどうかは、どのような「問い」を投げかけるかによって変わります。ポジティブな「問い」を使うことで、相手が話しやすくなり、建設的な対話が生まれやすくなります。
たとえば、「このプロジェクトを進めるうえで、良かった点は何ですか?」といった質問は、成果を前向きに振り返る機会になります。一方で、「なぜうまくいかなかったのですか?」という問いかけは、相手を責める印象を与えかねません。
また、質問をすることで「あなたに興味をもっています」という好印象を与えることができます。その結果、相手も好意を持ってくれると、あなたに対して興味をもって質問してくれるようになり、人間関係が築きやすくなるというメリットがあります。
相手が話しやすくなるような前向きな問いを意識することで、会話が円滑になり、職場の雰囲気も良くなるでしょう。
トラブルを回避するための傾聴力と対話術
職場でのトラブルを未然に防ぐためには、相手の話をよく聞く「傾聴力」と、適切に対応する「対話術」が欠かせません。傾聴力とは、ただ聞くのではなく、相手の気持ちや意図を理解しながら話を受け止めるスキルです。
具体的には、「相手の話を遮らず、うなずきながら聞く」「相手の言葉を繰り返して確認する」といった方法が効果的です。
また、対話を進める際には、相手の意見を尊重しつつ、自分の考えを伝えるバランスが重要です。相手を否定せず、「なるほど、そういう考え方もありますね」といった共感の言葉を挟むことで、対話がスムーズになります。
ビジネスパーソンに必要な対話力については、以下のコラムでも解説しています。
ビジネスパーソンになぜ対話力が必要か
信頼関係を築くための言葉の選び方
職場の人間関係を良好にするためには、日々の言葉遣いも大切です。信頼関係を築くためには、相手を尊重する言葉を選び、無意識のうちに相手を傷つけないように注意するとよいでしょう。
たとえば、「やっておいてください」よりも「お手数ですが、お願いします」といった表現の方が、相手に配慮が伝わります。また、感謝の気持ちを伝えることも信頼関係の構築に役立ちます。「ありがとうございます」「助かりました」といった一言を添えるだけで、職場の雰囲気が良くなることがあります。
適切な言葉遣いを意識することで、相手との関係が円滑になり、働きやすい環境がつくれるでしょう。
職場の人間関係ストレスチェック

職場の人間関係によるストレスは自分で気づかないうちにたまってしまいがちです。また、職場の人間関係が悪化していても、職場の中にいるメンバーは客観的に気づきにくいという問題もあります。
そのような場合は、職場の人間関係でどれほどストレスを感じているか、セルフチェックや職場内での簡易チェックを活用するとよいでしょう。
厚生労働省では、職場の人間関係ストレスチェックとして、個人向けの簡易版チェックリストと事業所で導入するストレスチェック実施プログラムを無料で公開しています。
「5分でできる職場のストレスチェック」は、4つのSTEPによる簡単な質問から職場におけるストレスレベルを測定可能です。厚生労働省が管轄するメンタルヘルスのポータルサイト「こころの耳」に掲載されています。
▼「5分でできる職場のストレスチェック」
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」は、平成27年12月より施行されたストレスチェック制度が事業者にて円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等が出来る無料プログラムです。
▼「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
職場の人間関係を長く続けていくためには、ストレスをゼロにしようとするのではなく、適度な距離感を保ちながら上手にストレスと向き合っていくことが大切です。
【まとめ】コミュニケーションの工夫や適度な距離感がポイント
職場の人間関係について、上手に割り切るやり方や改善するコツなどを解説しました。
職場の人間関係は、プライベートのように自分で自由に付き合い方を変えられない場合も多いため、ある程度割り切るマインドセットを保ちつつ、孤立しないように適度な距離感を意識するようにしましょう。
傾聴力を発揮する、ポジティブな表現を多用するなど、ちょっとしたコミュニケーション方法の工夫で、対人関係が驚くほど改善することもありますので、試してみてください。
ただし、職場の人間関係は、パワハラやモラハラなどメンバーや組織自体に問題があるケースもありますので、その場合は早急に適切な窓口などに相談するようにしましょう。