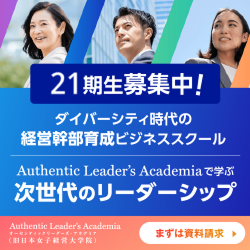「あなたがそこにいることを私は認識していますよ」 上司として部下との精神的距離を縮めるためにできること
- なつき 高橋
- 2025年2月19日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年2月19日

総研コラムでは、わたし・みらい・創造センター(企業教育総合研究所)(WMSC)の研究員らが「企業で働く個人のユニークネスと組織のオリジナリティを最大限に発揮する」ためのヒントとなるような知見や情報を提供します。誰もが本質的に「職場のコミュニケーションは大切」だと感じています。
と同時に、なぜ大切なのか、そしてどうすればコミュニケーションがよくなるのかとお悩みの方も多いと思います。
本記事では、上司が部下に、部下が上司に感じているコミュニケーションの課題と、課題を解決するためにまずどうしたらよいのかを、コミュニケーションを重視する心理療法の視点からご紹介します。
執筆者:佐々木 啓
アイデンティティー・パートナーズ株式会社 わたし・みらい・創造センター(企業教育総合研究所) 研究員
【 目 次 】
上司が部下に対して感じているコミュニケーションの課題

エン・ジャパン株式会社の「1800人のビジネスパーソンに聞いた「上司・部下間のコミュニケーション」調査」(2024年7月実施)によると、「現在の部下とのコミュニケーションに課題を感じますか?」という問いに、上司の68%が「感じる」(大いに感じる:29%、どちらかと言えば感じる:39%)と回答しました。

具体的な課題としては、「相手との精神的な距離を感じる」が40%と最多でした。

出典:エン・ジャパン株式会社「1800人のビジネスパーソンに聞いた「上司・部下間のコミュニケーション」調査」
上司として感じている部下との精神的な距離は、当然部下が感じている上司との精神的な距離です。
そのような状態での部下指導や1on1の実施、部署内のチームビルディングや仕事へのエンゲージメント形成は非常に困難なものとなるでしょう。
また部下は精神的距離や心理的安全性から必要最低限の報告しかしなくなり、質問や相談の機会も減ると思われます。その状態は、情報の共有や認識の統一、チームメンバーの連携、技術や知識の継承などを阻害しかねません。
では、上司として部下との精神的距離を縮めるために、まずできることは何なのでしょうか?
相手の存在を認める働きかけ ストロークとは

一つのアイデアとして提案できるのは「無条件の肯定的ストロークの交換」というものです。
ここでいうストローク(stroke)とは、交流分析(Transactional Analysis)という心理療法の専門用語です。なぜビジネスシーンに医療分野の話題が? と訝しがる方もいらっしゃるかもしれません。
交流分析は1950年代半ばの米国で誕生した、人と人とのやり取り=交流を分析することによって個人の成長と変化を促す心理療法です。
そして、この交流分析が画期的だったのは、「人と人とのやり取りは診察室に限ったことではない」と考えたことです。
交流分析は、私たちがあらゆる状況で行なっている交流に対して、よりよく生きるための考え方とその方法を提供してくれます。もちろんビジネスシーンにおいても、です。
その交流分析では、「相手の存在を認める働きかけ」のことをストロークと呼びます。平たく言うなら「人に向ける注意」のことです。目を合わせる、話をする、握手をするなど、私たちは日々ストロークを出し、受け取りながら生きています。すべてのコミュニケーションはストロークの交換と言えるでしょう。
ストロークにはさまざまな分類と組み合わせがあります(無条件/条件付き、言語的/非言語的、肯定的/否定的)。
その中でも人間関係の土台を作り、人との精神的距離を縮めるための第一歩となるのが、先に挙げた「無条件の肯定的ストロークの交換」です。
無条件とは、相手はストロークをもらうために何かをする必要がないということです。
たとえば、赤ちゃんはただ寝ているだけで優しいまなざしで見つめられ、だっこをしてもらえますよね。1日何回呼吸をしたからとか、寝返りの芸術点が高いから、などの条件はありません。
そこにいるだけでもらうことができるストローク、それが「無条件」という意味です。
肯定的とは、もらった人が良い気分になるストロークのことです。ほめる、称える、認める、いたわる、慰める、笑顔を向ける、ハグするなどなど。
逆に否定的とは、もらった人が嫌な気分になるストロークのこと。怒る、叱る、怒鳴る、にらむ、あからさまに無視をする、殴る……。
つまり、「無条件の肯定的ストロークの交換」とは、「もらうために何かする必要のない、もらった人が良い気分になるストロークを交換すること」です。しかし、果たして職場にそんな都合のよいものが……実はあるのです。
すべてはあいさつから始まる

それは「あいさつ」です。
おはよう、こんにちは、さようなら。
お疲れさま、また明日、良い週末を。
声をかけることだけがあいさつではありません。目が合ったときの目礼、手を振るなどのジェスチャーもそうですね。あいさつは、「あなたがそこにいることを私は認識していますよ」というメッセージです。
え? そんなこと? と思ったあなた。実際にあいさつを口に出したり、態度に表したりしていますか? ストロークは相手が受け取って初めて「ストローク」になるのです。
この「無条件の肯定的ストローク」が普段から交換されていることは、部下との精神的距離を縮めるための第一歩です。それが人間関係の土台を作り、職場の心理的安全性につながります。部署内のチームビルディングや仕事へのエンゲージメント形成は、あくまでその先に訪れるものです。一足とびにはいきません。

私たちは赤ちゃんのころ、無条件の優しいほほえみやふれあいのなかで育ちました。それは大人になったからといって不必要になったわけではありません。人は死ぬまでストロークを求め続けます。
もしあなたの職場でコミュニケーションの課題があって、無条件の肯定的ストロークの交換が足りないと感じられるのでしたら、「あなたがそこにいることを私は認識していますよ」というメッセージ=気持ちのよいあいさつから始められてはいかがでしょうか?
私たち企業教育総合研究所(WMS)では、「心理療法・臨床心理学をビジネスの分野に応用する」という研究も行っています。
今後もアイデアをコラムとして、実践方法を研修として発表していきます。
IDPのセミナー・イベント情報はこちら
参考文献
・エン・ジャパン株式会社「1800人のビジネスパーソンに聞いた「上司・部下間のコミュニケーション」調査(2024年7月)」
・日本交流分析学会(2017年)『交流分析基礎テキスト』
▼この記事を書いた人
佐々木 啓(ささき あきら)
〈プロフィール〉
1998年より、教育研修会社にて心理療法研修のマネジメントに従事。国内外の一流心理療法家の技能と研修ノウハウを学ぶ。10年間の修行の後、2008年から自らも講師として活動を開始。現在に至る。その人の特性や課題に最もマッチしたアプローチを、多種多彩な心理療法から選んで構成する研修やコーチングが強み。「不健康な状態で行う思考の質などたかが知れている」を信条に、まず個人の心身を整える実習やエクササイズが得意。
2015年 ICC認定国際コーチ資格取得
2016年 同国際チームコーチ資格取得
2019年 公認心理師資格取得