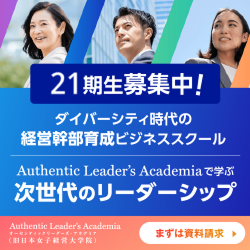中堅社員にもっと広い視野を持たせるには?現場と経営をつなぐ実践アプローチ
- なつき 高橋
- 2025年9月30日
- 読了時間: 6分

中堅社員は、現場の中心で活躍しながら組織の中核を担う重要な存在です。
しかし、日々の業務に追われるあまり、自部門の視点に偏ってしまい、全社的な方向性や経営視点を見失うことも少なくありません。
本記事では、中堅社員がより広い視野を持ち、現場と経営をつなぐ力を発揮できるようになるための具体的な方法と事例をご紹介します。
【 目 次 】
中堅社員にもっと広い視野を持たせるには?

中堅社員に広い視野を持たせることは、組織全体の成長と変革に不可欠です。
なぜ視野が必要なのか、どうすれば育てられるのか、その具体的な方法と効果を解説します。
なぜ中堅社員に広い視野が必要なのか
現場経験が豊富な中堅社員は、「全体最適」を考えられる存在に育てるべきです。
中堅社員は現場業務の中心を担い、若手育成や後輩指導も行います。しかし、現場に近いほど自部門最適に陥りやすく、組織全体の動きや経営視点を見失うことがあります。広い視野を持つことで、組織全体の課題解決や新しい価値創出に貢献できる人材へ成長します。
近年の調査でも、中堅層の社員は業務負担やストレスを抱えやすく、長時間労働傾向にあることが示されています。これは、目の前の業務に追われてしまい、経営全体を見渡す余裕が持ちにくい状況を反映しています。(※1)
一方で、中堅社員に経営視点を持たせることが企業競争力の強化につながると経済産業省も指摘しています。人材育成政策の中で「ミドル層が経営層と現場をつなぐ役割」を担うことが重要とされており、単なる現場リーダーではなく、経営理解を持つ中核人材の育成が課題となっています。(※2)
※1 出典:厚生労働省|『令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況』
広い視野を持たせるためのアプローチ

部門横断・経営層との対話・市場動向の理解が、視野を広げる効果的な方法です。実践的な場が中堅社員の成長を促します。
部門横断プロジェクトへの参加
部署を越えた取り組みは、他部門の事情や課題への理解を深めます。
具体例:
新商品開発プロジェクトに、営業・製造・人事など複数部署からメンバーを選出。
全社的なDX推進チームに、現場リーダー層として中堅社員を参画させる。
部署横断での改善活動(コスト削減・品質向上・業務効率化)の委員会に参加。
経営層との対話機会を設ける
経営判断の背景を知ることで、自分の業務の位置づけを俯瞰できます。
具体例:
月1回、部長や役員と中堅社員が直接議論する「タウンホールミーティング」を開催。
経営会議の一部をオブザーバーとして中堅社員に公開。
役員との少人数ランチミーティングを企画し、経営視点での質疑応答を実施。
業界動向や市場情報を学ぶ
外部環境の変化を知ることで、組織の方向性を理解しやすくなります。
具体例:
業界団体や学会が主催するセミナーへの参加を推奨。
他社事例を扱うケーススタディ研修を実施。
社内で「マーケット動向共有会」を定期開催し、営業や企画部門が最新情報を共有。
成功事例:「ビジネスモデル思考プログラム」の効果
管理職研修での成果は、中堅社員育成にも応用できます。
たとえば、ある大手専門商社では管理職を対象に「ビジネスモデル思考プログラム」を導入。
自部門の成果しか語れなかった参加者が、全社の事業を横断的に語れるようになりました。(※)
この成果は中堅層にとっても有効です。管理職と同様に、中堅社員も「全社を俯瞰する力」を求められています。早期から経営視点を体感することで、自部門最適にとどまらず、組織全体を見渡す力を育てる土台になります。
※出典:アイデンティティー・パートナーズ株式会社|ビジネスモデル思考プログラム
広い視野を育てるための研修選びのポイント

体験型・対話型の研修は、中堅社員に経営と現場をつなぐ視点を育て、行動変容を引き出します。単なる座学や知識のインプットにとどまらず、現場の課題を自分ごととして考え、経営層や他部門の視点と結びつける仕掛けが重要です。
具体的には、以下のような条件を備えた研修が効果的です。
経営戦略と現場課題を結びつける内容であること
経営層の方針や全社戦略を題材に、自部門の仕事との関連性を考えるプログラムは、中堅社員に「自分の業務が会社全体にどう貢献しているか」を実感させます。たとえば、経営計画をケーススタディとして分析し、自部門の役割をディスカッションする形式が有効です。
複数部門や職種が混ざって参加できること
同じ部門の中だけで完結する研修は、どうしても視野が偏ります。他部門の社員と議論や共同ワークを行うことで、自分の立場からは見えなかった課題や視点を得られます。これは「越境学習」とも呼ばれ、イノベーションや組織全体の活性化に寄与すると報告されています。(※1)
実践的なアウトプットの場があること
学んだ知識や気づきを「自分の業務にどう活かすか」を明確にするプロセスがなければ、研修効果は限定的です。成果発表やアクションプランの策定、現場での実践と振り返りを組み合わせることで、行動変容が定着しやすくなります。(※2)
実際に、経営層との合同ワークや部門横断のケーススタディを取り入れたプログラムでは、研修後に「自分の仕事を全社視点で考える習慣がついた」と回答する参加者が多数報告されています。こうした仕掛けを備えた研修は、中堅社員が「現場と経営をつなぐ存在」へと成長するための重要なステップになります。
※1 出典:経済産業省|「越境学習による人材育成に関する調査」(2020年)
※2 出典:リクルートワークス研究所|「人材育成における学習の越境と実践」(2019年)
よくある質問(FAQ)
Q1. 中堅社員が視野を広げられない原因は?
A. 自部門業務に集中しすぎることや、経営情報への接触機会が少ないことが主な要因です。
Q2. 視野を広げるには、どのくらいの期間が必要?
A. 数か月〜1年程度、継続的な部門越境や経営層との対話機会が効果的です。
Q3. 研修だけで視野は広がる?
A. 研修はきっかけになりますが、実務での活用や上司・同僚との継続的な対話が不可欠です。
まとめ:中堅社員の成長が組織全体を押し上げる
中堅社員に広い視野を持たせるには、部門越境・経営視点・外部環境理解を組み合わせた継続的な機会が必要です。
組織全体の方向性に沿った判断や提案ができる視野の広い中堅社員は、変化の時代において、組織の競争力を支える大きな力となります。