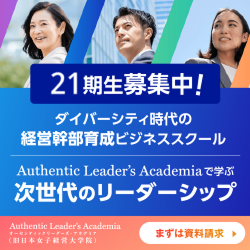人的資本経営とは?考え方や新たに導入された開示義務などについてわかりやすく解説
- saganmm
- 2025年4月21日
- 読了時間: 17分
更新日:2025年5月14日

人的資本経営とは、簡単にいうと人を資本として捉える経営手法です。
人を資本として捉える、という意味はなんとなくわかっていても、従来の人材育成や人事方針と何が違うのかわからない、と感じている人事部の方も多いことでしょう。
上場企業では新たに人的資本経営に関する開示義務が課せられ、具体的な開示項目や指標について頭を悩ませている経営層もいるかもしれません。
本コラムでは、人的資本経営の考え方について、経済産業省の定義や伊藤レポートなどに基づいてわかりやすく解説します。
人的資本経営の開示義務やISOガイドライン、具体的な導入の企業事例などについても解説しますので、参考にしてください。
【 目 次 】
人的資本経営とは簡単にいうと?
人的資本経営が求められている背景
経済産業省の人的資本経営の定義
人的資本経営と伊藤レポート
経済産業省の人的資本経営コンソーシアムとは
ISOの情報開示ガイドライン
人的資本経営に関する日本での開示義務
有価証券報告書で開示する指標
荏原製作所
東京海上ホールディングス
オムロン
人的資本経営における人事の役割とは
人的資本経営と社員エンゲージメント
経営と人事の連携が鍵
人的資本経営とは?意味と求められている背景

人的資本経営については、経済産業省がコンソーシアムを立ち上げ、民間でも人的資本経営に関するセミナーが実施されたり経営書が発刊されたりするなど、話題になっています。
まずは人的資本経営とは何かをおさらいし、人的資本経営が求められている背景をわかりやすく解説します。
人的資本経営とは簡単にいうと?
人的資本経営とは、簡単にいうと人材を資本として捉え、企業価値の向上につなげる考え方です。
人材を資本として捉える考え方自体は、経済学上で「Human Capital」または「Human Aseets」といわれ、以前からありました。経済学の祖といわれるアダム・スミスも、資本の種類の一つとして「社会のすべての構成員が獲得した有用な能力」を挙げています。※
ただし、従来の人的資本の考え方は、メンバーの能力を経済的に評価するというレベルにとどまっていました。
人的資本をこのような考え方から大きく前進させる一つのきっかけとなったのが、2001年にOECDが発表した『The Well-being of Nations』というレポートです。このレポートにより、人的資本の経済的価値の大きさや重要性が見直されはじめました。※※
近年注目されている人的資本経営は、人材の経済的価値を認めるというだけでなく、最重要の資本の一つとして捉える経営手法をいいます。人材育成や組織活性化など人材の活用を経営課題のメインに据え、中長期的な企業価値の向上につなげていくのが人的資本経営なのです。
人的資本経営が求められている背景

人的資本経営が求められている背景には、資本市場と労働市場の両方で人的資本への注目が高まっていることがあります。
VUCAの時代といわれ、企業を取り巻く環境がますます複雑化・多様化するなか、企業経営における「人」の重要度が高まっているのです。投資家が人的資本経営に注目しはじめるとともに、人的資本における情報開示が企業サイドに求められています。
また、労働市場では少子高齢化に伴う労働力の不足や市場の多様化などを受けて、人的資本経営へのニーズが高まっています。人材獲得競争の激化するなか、働き手も自らが働く環境やキャリアアップの可能性を慎重に見極めるようになり、企業の人材戦略に強く関心を寄せているのです。
また、女性や高齢者・外国人など多様な人材に対応するためにも、人材を資本として捉え最大限に活用する人的資本経営が注目されています。
▼人的資本経営と多様な人材の活用、ダイバーシティとの関わりについては以下のコラムが参考になります。
人的資本経営と経済産業省・伊藤レポート

OECDのレポートをきっかけに国際的に人的資本経営が注目を浴びるようになり、日本でも経済産業省が人的資本経営を推進するさまざまな取り組みを行っています。
ここでは、経済産業省における人的資本経営の定義、経済産業省が主導し2020年にまとめられた「伊藤レポート」、支援策としての「人的資本経営コンソーシアム」の設立について解説します。
経済産業省の人的資本経営の定義
経済産業省では、人的資本経営を以下のように定義しています。
人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です引用元:経済産業省 | 人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~
企業が急激な事業環境変化に対応し持続的な成長を実現するためには、新しい人材ポートフォリオの構築やイノベーションの創出が不可欠です。
経済産業省では、人的資本経営を推進するため、検討会や研究会の発足、レポートや調査のとりまとめ、取り組み事例の共有やセミナー実施など、さまざまな取り組みを実施しています。
人的資本経営と伊藤レポート
日本の人的資本経営を理解する上で欠かせないのが「人材版伊藤レポート」です。これは、経済産業省が2020年に発表した報告書で、企業が人的資本を活用して成長するための指針を示しています。
もともと「伊藤レポート」は、2014年に「持続的成長への競争力とインセンティブ 〜企業と投資家の望ましい関係構築〜」として公表され、日本企業の競争力向上を目的としたレポートでした。その後、2020年に「人材戦略」に特化したものとして発表されたのが「人材版伊藤レポート」です。
2020年の「人材版伊藤レポート」は、経済界でも大きな反響があり、2022年5月には「人材版伊藤レポート2.0」が、同9月には、「伊藤レポート 3.0(SX 版伊藤レポート)」が相次いで公表されています。
「人材版伊藤レポート2.0」では、企業が人的資本経営を推進するため以下の3つの視点が求められるとしています。※
経営戦略と人材戦略の連動
企業が成長戦略を策定する際、人材戦略を切り離して考えるのではなく、経営戦略の一部として統合することが重要です。
経営陣が主導し、経営戦略とのつながりを意識しながら、CHROの設置、全社的経営課題の抽出、具体的なアクションやKPI設定などを行っていく必要があります。
「 As is - To be ギャップ」の定量把握のための取り組み
人的資本経営を推進するにあたっては、目指すべき姿(To be)の設定と現在の姿(As is)とのギャップの把握を定量的に行うことが必要です。
そのためには、経営戦略実現の障害となる人材面の課題を特定したうえで、人材関連の改善KPIを把握・測定するための情報基盤の整備、定量把握する項目の一覧化などを行います。
企業文化への定着のための取り組み
人的資本経営により持続的に企業価値を向上させていくためには、人材戦略を策定する段階から、目指す企業文化を見据えることが重要です。
そのためには、企業文化の定義や、トップマネジメントとの企業文化に関する対話の設定、社員の具体的な行動や姿勢への紐づけなどの観点から、企業文化を醸成し定着させる取り組みが求められます。
経済産業省の人的資本経営コンソーシアムとは
経済産業省は、2022年、企業が人的資本経営を実践するための支援策として「人的資本経営コンソーシアム」を設立しました。
このコンソーシアムは、企業や研究機関、投資家が連携し、人的資本経営に関する情報共有や実践事例の提供を行う場です。
経済産業省および金融庁がオブザーバーとして参加し、人的資本経営の実践企業による事例共有、人的資本情報の開示に関するガイドラインの提供、企業間協力に向けた議論などを行っています。
経済産業省の人的資本経営コンソーシアムについて、詳しくは専用サイトがありますのでご参照ください。
人的資本経営の開示義務とは

人的資本経営の注目が高まるにつれ、人的資本経営にかかわる情報開示が求められるようになってきています。投資家やステークホルダーにとって、企業がどのような人材戦略を実施しているかを可視化する必要があるからです。
ここでは、国際的な基準であるISOの情報開示ガイドラインと、日本での情報開示の動きについて解説します。
ISOの情報開示ガイドライン
ISO(国際標準化機構)は、2018年に世界初の人的資本情報開示ガイドラインとして「ISO30414」を公表しました。これは、企業が人的資本に関するデータを開示する際の国際的な基準を示すものです。
ISO30414では、人的資本の情報開示において、以下のような分野での指標を提供しています。※
・コンプライアンスと倫理 ・コスト ・多様性(ダイバーシティ) ・リーダーシップ ・組織文化 ・組織の健全性や従業員のウェルビーイング ・生産性 ・採用・離職(採用率・離職率・定着率など) ・能力開発 ・後継者の育成 ・労働力の利便性(職務内容や働き方の多様性など) |
ISO30414は、国際的な投資家にとって企業の人的資本戦略を評価する際の指標になっており、グローバル企業の人的資本情報を統一的な指標で評価するために役立ちます。
2024年には、日清食品ホールディングス株式会社が食品企業として世界で初めてISO30414を取得するなど、企業規模や業界を問わず、日本国内でも取得する企業が増えています。※※
人的資本経営に関する日本での開示義務
ISO30414の公表など、国際的な情報開示ニーズの高まりを受け、日本では、2022年8月に内閣官房が「人的資本可視化指針」を公表しました。※
「人的資本可視化指針」では、人的資本情報の開示について、既存の基準やガイドラインの活用方法を含めた企業の対応の方向性を示しています。
さらに内閣府令などの改正により、有価証券報告書などにおいて「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設されました。2023年3月期決算以降、上場企業には人的資本に関する情報開示が義務付けられています。※※
※参考:内閣府 | 人的資本可視化指針
有価証券報告書で開示する指標
有価証券報告書で開示する指標としては、まず「従業員の状況」で以下の3つの項目が新たに追加されています。
女性管理職比率
男性育児休業取得率
男女間賃金格差
サステナビリティ情報については「記載欄」を新設し、「戦略」および「指標及び目標」については、各企業が重要性を踏まえて開示を判断することとなっています。
ただし、人的資本については、「人材育成方針」や「社内環境整備方針」および当該方針に関する指標の内容や当該指標による目標・実績の開示が全企業に義務づけられているのが特徴です。
前出の内閣府による「人的資本可視化指針」では、以下のような開示事項が例として挙げられています。
【人的資本の開示事項例】
分野 | 開示事項の例 |
人材育成 | 研修時間、研修費用、研修参加率、人材確保・定着の取り組みの説明など |
従業員エンゲージメント | ISOやサステナビリティ会計基準審査会(SASB)などに基づく従業員エンゲージメント指標 |
流動性 | 離職率、定着率、新規雇用の総数・比率、離職の総数、採用・離職コスト、後継者有効率、後継者カバー率など |
ダイバーシティ | 属性別の従業員・経営層の比率、正社員・非正規社員などの福利厚生の差、育児休業などの後の復職率・定着率、男女別育児休業取得員従業数など |
健康・安全 | 労働災害の発生件数・割合、死亡数、医療・ヘルスケアサービスの利用促進、その適用範囲の説明など |
コンプライアンス・労働慣行 | 深刻な人権問題の件数、差別事例の件数・対応措置、団体労働協約の対象となる従業員の割合など |
有価証券報告書における人的資本の開示は、投資家に対して企業の人材戦略を透明化する役割を果たします。これにより、投資家は企業の将来的な成長性を評価しやすくなり、企業は「人的資本に投資することが競争力向上につながる」という考えを示せます。
※参考:内閣府 | 人的資本可視化指針
人的資本経営の企業事例

人的資本経営の重要性を理解していても、実際に企業内でどのような取り組みをすればよいのかわからない、という経営者も多いでしょう。
前出の経済産業省主導による『人材版伊藤レポート2.0』では、人的資本経営を実践する企業の事例を紹介しています。
ここでは、企業事例集のなかから、荏原製作所・東京海上ホールディングス・オムロンの3社を取り上げてご紹介します。
事例1 荏原製作所
精密・電子機械製造をグローバルに展開している荏原製作所では、以下のような人的資本経営の取り組みを行っています。
海外拠点のキーポジション・人材も含めたプランニング、抜擢・育成 社外連携と人材育成 アルムナイ制度の実施
海外拠点の人材を適切に採用・配置するため、事業上重要なグローバルキーポジションへの後継者計画を整備し、後継者候補の全ての人材を社長自身でレビューしています。
さらに、学術分野事業に関連する専門家を招聘し、事業に直結する技術課題に関する共同研究を実施するなど、社外と連携しながら人材育成を行っているのが特徴です。
また、独自のアルムナイ制度「エバルムナイ」(荏原製作所のアルムナイ)を実施し、退職者の再雇用を行うなど、多様な人材の獲得を推進しています。
事例2 東京海上ホールディングス
グループで保険・金融事業を展開する東京海上ホールディングスは、以下のような取り組みで、戦略的人事と多様な人材育成を推進しています。
戦略的な人事制度による人材ポートフォリオ最適化 経営人材育成責任者と目標が明確なダイバーシティ推進 多様性を活かす基盤としてのパーパス浸透に向けた対話
年齢や在籍年数にかかわらず能力のある人材を管理職に登用するトップタレント獲得のための人事制度導入、幅広い世代での経営人材育成プログラムの実施などにより、人材ポートフォリオの最適化を図っています。
ダイバーシティ推進においては、2021年にCDIO(Chief Diversity& Inclusion Officer)を設置、2030年までに女性管理職比率30%目標など具体的なKPIを掲げ、責任や目標を明確化しているのが特徴です。
このほか、全社員共通のパーパスを浸透させるため、まじめな話を気楽にする対話の場(「マジきら会」)を設置するなど、人的資本経営を実現する社内文化の醸成にも取り組んでいます。
事例3 オムロン
ヘルスケア製品製造事業を営むオムロンでは、以下のような点をポイントに人的資本経営を推進しています。
社員自ら目標を立てる(旗を立てる)過程で、企業理念を浸透 グローバルリーダーの人財育成、現地化を人財戦略として位置付け 持続的成長を支える多様・多才な人財を支援するインフラを整備
同社では、グローバル全社で企業理念実践のためのストーリーを全社員で共有し合い、自ら目標を立てることで企業理念を浸透させるよう取り組んでいます。
そのような取り組みで浸透した企業理念を体現し、組織を索引するグローバルリーダーを育成するため、「グローバルコアポジション」を約200設定し、適切な人財を発掘し、配置・育成しています。
また、企業理念の実践に取り組むチームをつくり上げるために、社員の能力、経験、志向を見える化したシステムを整備しました。
人的資本経営の課題
人的資本経営は、企業の持続的成長のために重要な経営手法ですが、実践にはさまざまな課題が伴います。
最後に、人的資本経営の課題として、人事の役割、社員エンゲージメントとの関わり、経営と人事の連携の重要性について解説します。
人的資本経営における人事の役割とは
人的資本経営において、人事部門の役割は大きく変化しています。
従来の人事部門は、採用や労務管理といった業務が中心でしたが、人的資本経営の考え方が浸透するにつれ、「人材戦略を経営戦略と統合する」ことが求められるようになりました。
企業の成長に必要なスキルや人材を見極め、適切な研修制度や人事制度を構築したり、社員のエンゲージメントを向上させる施策を行ったりするためには、企業理念や経営戦略への深い理解が不可欠です。
従業員を単なるコストではなく「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出す役割、つまり人的資本経営の根本にある考えを実践することが、これからの人事部門に求められています。
人的資本経営と社員エンゲージメント
人的資本経営の実践と社員のエンゲージメント向上は密接に結びついています。エンゲージメントが高い従業員は、業務に対して積極的に取り組み、生産性やイノベーションの向上に貢献するでしょう。
そのためには、働きがいのある環境の整備、キャリア成長の支援、評価・報酬制度の最適化などを人事が行い、社員のモチベーション向上を図る必要があります。
人的資本経営を推進するためには、単に従業員のスキル向上を目指すだけでなく、「会社の成長=従業員の成長」という関係性を築くことが重要です。
アイデンティティー・パートナーズが提供する「ビジネスモデル思考プログラム」は、自社の優位性、MVVを理解し、改めて組織の一部であることを認知することで、組織の一員としての役割を前向きに捉えなおし、エンゲージメント醸成に役立ちます。
▼社員エンゲージメントの測定方法や高める方法などについては以下のコラムでも解説しています。
経営と人事の連携が鍵
人的資本経営を成功させるには、経営層と人事部門の密接な連携が欠かせません。従来のように人事部が単独で人材戦略を立案するのではなく、経営戦略と一体化させる必要があります。
経営と人事の連携強化をするためのポイントとして、以下のような点に配慮するとよいでしょう。
経営層が人的資本経営をリード
データに基づいた意思決定
経営戦略と人材戦略の統合
人的資本経営はまず何よりも経営マターです。人事部主導で行うのではなく、CEOや経営幹部が人的資本経営の重要性を理解し、人事部と連携しながら戦略を推進するよう取り組みましょう。
意思決定を行う際には、従業員のスキルやパフォーマンスデータを活用し、科学的なアプローチで人事施策を策定するのがポイントです。企業の成長目標に基づき、必要な人材の確保・育成を計画的に行います。
最後に、人的資本経営は、単なる人事施策ではなく、経営全体の課題として取り組むことが重要です。経営と人事が連携し、組織全体で人的資本を最大限に活用することで、企業の競争力が高められます。
人材戦略に経営戦略を織り込むことはもちろん、経営戦略自体に人的資本経営の考え方を取り入れましょう。
【まとめ】人的資本経営の導入で変わる経営と人事
人的資本経営が注目されている背景や、日本での開示義務や企業での導入事例などを解説しました。
人材を資本として捉え戦略的に活用することで、企業の持続的成長を実現する人的資本経営。人手不足や市場の多様化などに伴い、今後さらに人的資本の価値を最大限に引き出すための仕組みづくりが求められてくでしょう。
人的資本経営を実践するためには、経営と人事両方が意識を変えていく必要があります。経営層はコストや利益だけでなく、人材の活用を最重要の経営マターとして認識することが必要です。一方、人事部も経営方針や会社全体の課題を意識して人材戦略を構築することが求められます。
アイデンティティー・パートナーズでは、組織で働く方々の「対話」を通じ、組織を活性化させ、企業の競争優位性を取り戻す、まさに人的資本経営の要となる人と組織に焦点をあてたソリューションを提供しています。
当社は、組織活性コンサルティングに加え、企業の研修内製化をお手伝いするコンテンツ開発、ダイバーシティの時代に対応できるリーダーを育てるアカデミア事業、それらサービスを下支えするシンクタンクやサーベイ機能など、多様な課題に対応できるサービス体系となっているのが特徴です。
人的資本経営の導入を検討中の経営者の方、人的資本経営に興味をお持ちの人事部の方など、それぞれの課題に合ったソリューションを提供させていただきますので、ぜひご相談ください。
オーセンティックリーダーズ・アカデミアについてはこちら