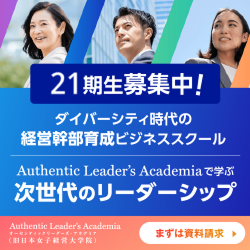コミュニケーションとは? 意味・目的・能力を高める方法を徹底解説
- saganmm
- 10月1日
- 読了時間: 17分

コミュニケーションはビジネス上でもよく聞く言葉です。
働き方が多様化するなかで、職場においてコミュニケーションをとる大切さをあらためて実感している人も多いでしょう。
コミュニケーション方法に悩み、自分自身のコミュニケーション能力を高める必要性や苦手意識を感じている人もいるかもしれません。
本コラムでは、コミュニケーションの言葉の意味やコミュニケーションを図る目的を整理し、能力が高い人の特徴や高める方法などについて解説します。
【 目 次 】
言葉の意味と語源
情報伝達との違い
なぜコミュニケーションを図ることが大切なのか
信頼関係の構築につながる
チームワークや協力を促進する
生産性・効率を高める
対話型(口頭での会話)
非言語(ノンバーバル)コミュニケーション
テキストやオンラインでのやりとり
ビジュアルを使ったコミュニケーション
コミュニケーションの4つの要素とは
コミュニケーション能力が高い人の特徴
信頼関係を築ける
職場や日常生活がスムーズになる
新しいアイディアや可能性を広げる
挨拶や声かけを習慣にする
話し方・伝え方を工夫する
ロールプレイやシミュレーション
もしかしてコミュニケーション障害?疑う前に
自己分析を通して改善点を知る
聴くことに重点を置く
【まとめ】コミュニケーションを再考する必要性

コミュニケーションとは?
コミュニケーションとは、お互いの考えや感情を伝え合い、理解を深めるための基本的な行為です。
言葉による会話だけでなく、表情や身振り、文章や映像など、あらゆる手段を通じて行われます。社会や職場では多様な価値観を持つ人々がかかわり合うため、コミュニケーションは単なる情報交換を超えて、信頼や協力を生み出す基盤となります。
最初に、コミュニケーションという言葉の意味や語源、情報伝達との違い、そして重要性について解説します。
言葉の意味と語源
コミュニケーションは、英語の「communication」をカタカナ表記したものですが、元々ラテン語の「communicare(共有する)」に由来しています。
この語源が示すとおり、コミュニケーションは一方的に伝えるのではなく、相手と情報や気持ちを分かち合うことに本質があります。
たとえば、相手に喜びを伝えるとき、単に「うれしい」と言うだけでなく、表情や声の抑揚を通じて相手も同じ感情を共有します。仕事上でも、進捗報告に事実だけでなく課題や感想を交えることで、チーム全体で状況を理解しやすくなります。
つまり、コミュニケーションは「伝える」よりも「共有する」ことに重点を置いた行為なのです。
情報伝達との違い
コミュニケーションを日本語で「情報伝達」と言い換えることがあります。しかし、コミュニケーションと情報伝達は似ているようで、範囲と目的に違いがあります。
情報伝達は事実やデータを正確に届けることを目的とします。一方で、先に説明したとおりコミュニケーションには感情や価値観の「共有」という意味が含まれています。
たとえば、上司が「この資料を明日までに提出してください」と伝えるのは情報伝達です。しかし、そこに「困ったことがあれば相談してください」と加えれば、単なる指示ではなく相互理解を生むコミュニケーションとなります。
「情報伝達」は内容を伝えることにとどまりますが、「コミュニケーション」は人間関係を深める要素を持ち、より広い意味でのやりとりとなります。
なぜコミュニケーションを図ることが大切なのか
ビジネスにおいてコミュニケーションを図ることは、誤解を防ぎ、信頼関係を築き、円滑な協力を生むために欠かせません。
職場内でもコミュニケーションを図ることは大切です。HR総研のアンケートでは、9割以上の人が「社内コミュニケーション不足は業務の障害」と考えていることがわかっています。※
情報共有がスムーズになれば業務の効率化につながり、誤解やトラブルも防げます。また、意見交換が活発になることで新しいアイディアが生まれ、組織全体の成長や雰囲気の向上につながるでしょう。
職場でコミュニケーションを図ることは、信頼関係や協力体制を築き、生産性を高める点からも重要です。
組織でコミュニケーションを円滑に進める目的

組織内や職場でもコミュニケーションが大事だとよくいわれますが、職場でのコミュニケーションを活性化する目的は何でしょうか。
組織内でコミュニケーションがスムーズであれば、信頼関係が育まれ、協力体制が強化され、生産性の向上へとつながります。逆に、意思疎通が不十分だと誤解や対立を招きやすくなるでしょう。
ここで、組織において円滑なコミュニケーションが持つ目的を確認しておきましょう。
信頼関係の構築につながる
円滑なコミュニケーションは、組織内の信頼関係の基盤を作る重要な要素です。
相手の話をしっかりと聞き、自分の考えを誠実に伝えるやりとりを続けることで、「自分は大切にされている」という安心感が生まれます。
たとえば、職場で上司が部下の意見に耳を傾け、丁寧に反応する姿勢を見せると、部下は上司に信頼を寄せやすくなるでしょう。
信頼は一度に得られるものではなく、日々のコミュニケーションの積み重ねによって築かれるのです。
チームワークや協力を促進する
スムーズなコミュニケーションは、チームワークや協力関係を強める効果があります。情報や意見を気軽に交換できる環境では、メンバーが互いの得意分野や弱点を理解しやすくなり、自然と役割分担が進みます。
たとえば、プロジェクトにおいて困難な課題が発生した際、普段から活発にコミュニケーションを取っていれば、即座に相談や協力が可能です。逆に意思疎通が不十分だと誤解や不満が生じ、連携が崩れやすくなります。
円滑なコミュニケーションを意識することは、チーム全体の結束を高め、成果を最大化するために不可欠です。
生産性・効率を高める
良好なコミュニケーションは、生産性や効率の向上にも直結します。情報が正確かつ迅速に伝われば、業務の重複や誤解を防ぎ、作業をスムーズに進められます。
たとえば、会議の場で進行状況や課題を明確に共有しておくと、あとから無駄な修正作業が発生しにくくなります。反対に、コミュニケーションが不足すれば、余計な時間や労力を費やすことになり、全体のパフォーマンスを下げてしまいます。
明確で丁寧なやりとりが、効率的な成果につながるのです。
コミュニケーションの4つの種類
コミュニケーションにはさまざまな形があり、状況や目的に応じて使い分けることが効果的です。
ここでは、コミュニケーションの伝え方を口頭・非言語・テキストやオンライン・ビジュアルの4つに分けて、特徴や使い分けるポイントなどを解説します。
対話型(口頭での会話)
口頭での会話によるコミュニケーションは、最も基本的で身近な手段です。直接相手と話すことで、言葉だけでなく声の抑揚や表情から感情や意図を汲み取りやすくなります。
たとえば、職場での会議は、その場で質問や反応を交わせるため、反応を見たり誤解を早く解消できたりする利点があります。
対話はリアルタイムでやりとりが可能である一方、言葉の選び方や伝え方を誤ると、意図が正しく伝わりません。
また、特に対話型のコミュニケーションの場合、言葉の内容だけでなく、表情や声のトーンなど、次に説明する「非言語(ノンバーバル)コミュニケーション」が与える影響が大きいことに注意が必要です。
非言語(ノンバーバル)コミュニケーション
言葉を使わずに意思や感情を伝える方法が、非言語コミュニケーションです。
代表的なものとして、表情、視線、身振り手振り、姿勢などがあります。
たとえば、笑顔は安心感や好意を示し、腕を組む姿勢は防御的な態度として受け取られるといわれています。人は会話の内容以上に、こうした非言語の要素から相手の気持ちを感じ取ることが多いのです。
そのため、自分の態度や表情が無意識にどのように映っているかに気を配ると同時に、相手の非言語的なサインを丁寧に読み取ることが、良好な関係を築くうえで大切です。
テキストでのやりとり
現代では、メールやチャット、SNSといったオンライン上のテキストを通じたコミュニケーションが日常的になっています。これらは時間や場所にとらわれずに利用でき、記録として残せる点が大きな利点です。
しかし、文字だけでは感情や細かいニュアンスを伝えるのが難しいときがあります。依頼や指示、指摘などについては、事実を直接的に伝えるだけでは、冷たく高圧的な印象を与えかねません。
テキストコミュニケーションでは、丁寧な言葉遣いや文末に一言追加するなどして、相手に配慮した温かみのあるやりとりを心がけることが大切です。
ビジュアルを使ったコミュニケーション
図や写真、イラスト、動画などを活用するビジュアルコミュニケーションは、複雑な情報を直感的に理解してもらえる手段です。
会議やプレゼンテーションでグラフや図表を用いれば、数値だけでは伝わりにくい内容を効果的に示せます。また、教育現場や広告などでも、ビジュアルを用いることで相手の関心を引きつけ、記憶に残りやすくなるでしょう。
言葉だけに頼らず視覚的な要素を取り入れることは、理解のスピードを高め、情報の説得力を強める効果があります。特に複雑な内容を共有するときほど、ビジュアルを組み合わせる工夫が効果的です。
コミュニケーション能力とは

最近では、コミュニケーション能力のことを「コミュ力」などといいますが、コミュニケーション能力とはそもそもどのような能力でしょうか。
コミュニケーション能力とは、相手に自分の意図を明確に伝えるだけでなく、相手の立場や期待を理解し、必要な対応をとる総合的なスキルです。
コミュニケーション能力について、アメリカの有名な経営学者ピーター・F・ドラッカーの有名な4つの原理に基づいて解説します。
コミュニケーションの4つの要素とは
ピーター・F・ドラッカーは代表的な著作『【エッセンシャル版】マネジメント 基本と原則』において、コミュニケーションには以下の4つの要素があるとしています。
コミュニケーションは知覚である
コミュニケーションは期待である
コミュニケーションは要求である
コミュニケーションは情報ではない
まずコミュニケーションが「知覚」であるという点では、いくら話し手が発信しても、受け手に理解されなければ成立しません。つまり、コミュニケーションを成立させるものはあくまで受け手であり、受け手の知覚範囲内によるのです。
またコミュニケーションは受け手の「期待」に左右されます。受け手は期待しているものだけを知覚し、期待していないものには抵抗を示すものです。このためコミュニケーションの相手が何を期待しているかを踏まえることが重要なのです。
さらにコミュニケーションは「要求」でもあり、相手の目的や価値観と合致した内容でなければ効果を持ちません。つまりコミュニケーションを効果的におこなうためには、相手の知覚や期待の範囲だけでなく、目的や価値観まで視野にいれる必要があります。
そして「コミュニケーションは情報ではない」という意味は、単なる事実の伝達にとどまらず、感情や文脈を含めた共有こそが、本質的なコミュニケーションである、ということです。
ドラッカーはコミュニケーションと情報は依存関係にあるとしながらも、2つは「別物」であり、情報は形式であり、感情や価値、期待などの人間的な要素はないが、コミュニケーションで重要なのはまさにその人間的な要素なのだとしています。
コミュニケーション能力が高い人の特徴
ドラッカーのコミュニケーションの4つの要素を踏まえて、コミュニケーション能力が高い人の特徴を考えてみましょう。
コミュニケーション能力が高い人とは、すなわち、4つの要素をバランスよく満たしてコミュニケーションできる人です。
相手の知覚や期待を想像し、理解できる
相手が知覚しやすい言葉や表現を選択できる
相手の目的や価値観を理解し、それを動かせる
単なる情報ではなく、感情や文脈を含めて相手に伝えられる
コミュニケーション能力が高い人は、自分自身の想像力や思考力を駆使して、相手の知覚や期待を理解できます。そのうえで、相手の目的や価値観などを動かし共感や感動を生み出せるような表現力や実行力が、コミュニケーション能力の高い人の特徴だといえるでしょう。
※参考:『【エッセンシャル版】マネジメント 基本と原則』P・F・ドラッカー(ダイヤモンド社)
コミュニケーション能力を高めるメリット
コミュニケーション能力を高めることは、人間関係や仕事の成果を大きく左右します。
信頼関係を築き、協力しやすい環境を生み出せるほか、職場や日常生活のスムーズな運営にもつながるでしょう。
ここで、コミュニケーション能力を高めるメリットについて確認しておきましょう。
信頼関係を築ける
コミュニケーション能力を高めると、仕事上でも相手との信頼関係を築きやすくなります。
自分の考えを明確に伝え、同時に相手の意見や感情を理解する姿勢を見せれば「この人となら安心して話せる」という印象を与えられるでしょう。
たとえば、上司が部下の声にしっかり耳を傾け、誠実に対応する姿勢を示すと、部下は信頼感を抱き、業務上の指示や連絡もスムーズにおこなえます。
信頼は一朝一夕に得られるものではなく、日々の誠実なコミュニケーションの積み重ねによって形づくられるのです。
リーダーシップを発揮できる
コミュニケーション能力を磨くことは、リーダーシップを発揮するうえでも大きな武器となります。
リーダーは、目標をわかりやすく伝え、チームをまとめる役割を担います。その際、単に指示を出すだけではなく、メンバー一人ひとりの意見や感情に耳を傾け、共感を示すことが不可欠です。
円滑なコミュニケーションによって信頼が生まれ、チーム全体の結束が強まることで、優れたリーダーシップを発揮できます。
新しいアイディアや可能性を広げる
コミュニケーション能力を高めることは、新しい発想やチャンスを生むきっかけにもなります。
活発に意見を交わす環境では、多様な視点が集まり、個人だけでは思いつかないアイディアが生まれる可能性が高まります。
たとえば、職場で自由に意見交換できる雰囲気があれば、既存の課題に対して新しい解決策が見つかりやすくなるでしょう。
円滑なコミュニケーションにより人との対話を通じて得られる気づきや学びは、新しい挑戦や自己成長につながります。
コミュニケーション能力を高める方法

コミュニケーション能力は生まれつきのものではなく、日々の習慣や工夫によって高められます。
特に、挨拶や声かけといった小さな実践、話し方や伝え方の工夫、そしてロールプレイやシミュレーションによるトレーニングは効果的です。
こうしたとり組みを重ねることで、人との関係がより円滑になり、自信を持ってやりとりできるようになります。
挨拶や声かけを習慣にする
コミュニケーション能力を高める第一歩は、日常の挨拶やちょっとした声かけを習慣にすることです。
簡単な「おはようございます」「ありがとう」といった言葉を交わすだけでも、相手に安心感や好意を伝えられます。
小さな積み重ねは信頼関係を築く土台となり、円滑なコミュニケーションへの第一歩となります。
話し方・伝え方を工夫する
相手に自分の考えを正しく理解してもらうには、話し方や伝え方に工夫が必要です。複雑な内容をそのまま伝えるのではなく、順序立てて説明したり、具体例を挙げたりして、相手にとって理解しやすい形に変えるように心がけましょう。
また、表情や声のトーンを意識して、相手に安心感や誠実さを伝えることも大切です。
コミュニケーション能力が高い人は、コミュニケーションには言葉だけでなく、非言語的な要素を含めた伝え方が重要であることを知っています。
ロールプレイやシミュレーション
実践的にコミュニケーション能力を磨く方法として、ロールプレイやシミュレーションがあります。想定される場面を再現し、実際にやりとりを試す練習法です。
たとえば、会議の発表を事前にシミュレーションしておけば、本番で落ち着いて話せるようになります。
このような練習は、単なる知識の習得にとどまらず、実際の場面で使える実践力を高めるのに効果的です。繰り返しおこなうことで自信がつき、自然にスムーズなやりとりができるようになります。
コミュニケーションが苦手な人の改善ポイント

コミュニケーションが苦手だと感じる人は少なくありません。
しかし、その多くは性格やちょっとした習慣に起因している場合が多く、工夫次第で改善できるのです。
大切なのは、すぐに自分を否定するのではなく、状況を整理して改善の糸口を見つけることです。
最後にコミュニケーションが苦手な人が、特に意識すると効果的なポイントを3つ紹介します。
もしかしてコミュニケーション障害? 疑う前に
会話がうまく続かない、相手の反応を気にしすぎて話せないなどの悩みを持つと、「自分はコミュニケーション障害かもしれない」と不安になることがあります。
しかし、多くの場合は病気ではなく、単に経験不足や緊張しやすい性格によるものです。
たとえば、初対面の人と話すときに沈黙が続いてしまうのは、話題の引き出しが少ないだけかもしれません。その場合、日頃からニュースや趣味の話題をストックしておくだけで改善できます。
また、知らない人相手に緊張や不安を覚えたり、急に発言を求められたら答えられなかったり、というのはコミュニケーション障害でなくても誰でも少なからず経験するものです。
病気と決めつける前に、冷静に自己分析をして改善策や自分に合ったコミュニケーション方法を考えてみてください。そのうえで、自分一人で解決が難しいと感じた場合は、専門家に相談するのも一つの手です。
自己分析を通して改善点を知る
コミュニケーションを改善するには、まず自分の傾向を理解することが有効です。
どのような場面で緊張するのか、どのような相手だと話しやすいのかを振り返ることで、改善のヒントが見つかります。
人前ではうまく話せないけれど一対一なら会話が続くという人は、まず少人数での練習を重ねると効果的です。また、相手の話を遮ってしまうクセや、自分の意見を言えない傾向などを把握すれば、具体的に直すべき行動が見えてきます。
自己分析を通じて改善点を知ることは、成長の第一歩となります。
聴くことに重点を置く
コミュニケーションが苦手な人は、自分がうまく話せるかどうかに意識を集中しがちです。しかし、相手の話をしっかり聴くことを優先するだけで、自然と会話が広がりやすくなります。
コミュニケーション能力が高い人というと、すらすら淀みなく話せる人をイメージしがちですが、コミュニケーションで重要なのはただ伝えるだけでなく、情報や感情を「共有」することです。
すぐに言葉や話題が出てこない場合は、相手の発言を繰り返したり「それはどういう意味ですか?」と質問を加えれば、会話は途切れにくくなります。聴く姿勢を積極的に示すことで相手は安心し、より多くのことを話してくれるようになるでしょう。
話すことよりもまず聴くことを大切にすれば、会話の負担が軽くなり、自然とコミュニケーションの質が向上していきます。
【まとめ】コミュニケーションを再考する必要性
コミュニケーションについて、意味や円滑にするメリット、コミュニケーション能力とは何かなどを解説しました。
職場でもさまざまな属性の人が働くようになり、SNSやオンライン会議ツールなど新しいコミュニケーション手段が加わるなか、企業で働く人はコミュニケーション方法や能力について改めて考え直す必要に迫られています。
アイデンティティー・パートナーズでは、組織で働く方々の「対話」を通じ、『 誰もが、いい声で話す 』組織を目指して、各種研修・コンサルティング・スクールなどのソリューションを提供しております。
組織活性化につながるコミュニケーション方法やメンバーのコミュニケーション能力を高める研修など、さまざまなコンサルティング・ご提案ができますので、ぜひお問い合わせください。