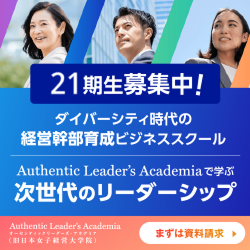女性管理職が少ない理由とは?割合・適性・育成方法まで解説
- 2025年5月20日
- 読了時間: 11分

「女性社員は多いのに女性管理職が少ない」「女性管理職比率の目標を定めているが思うように伸びていない」
ダイバーシティや女性活躍推進を進める企業で、このような悩みをお持ちの人事部や経営者の方も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、日本企業の女性管理職割合のデータ分析、女性管理職が少ない理由や女性管理職を増やすための企業の取り組み例などを解説します。
【 目 次 】
日本における女性管理職の割合推移
女性管理職比率 都道府県別(厚生労働省特別集計)
女性管理職比率の国際的比較
働き続けにくい制度と家庭・育児の両立問題
ロールモデルの不在で管理職になりたがらない女性が多い
性別役割分担意識やバイアスがもたらす影響
冷静な判断力と感情コントロール
チームマネジメント力と信頼関係の構築力
長期的視野で考えられる思考力・責任感
公平な評価制度と昇進機会の提供
育児・介護と両立できる働き方の支援
ロールモデルの確立と継続的な教育投資
管理職における女性の割合・比率

女性活躍推進が叫ばれているなか、日本における女性管理職の比率はどのように変化しているのでしょうか。
まずは、女性管理職の割合推移や地域差、国際比較のデータをもとに現状を整理していきましょう。。
女性管理職比率 都道府県別(厚生労働省特別集計)
日本の女性管理職の割合は、少しずつ上昇しているものの、依然としていくつか課題が残ります。
厚生労働省の調査によれば、民間企業(企業規模10人以上)の女性管理職比率は、2009年時点では課長職相当で6.1%、部長職相当で4.5%であったのに対し、2023年時点では課長職相当で12.0%、部長職相当で7.9%にアップしました。※
企業の規模別にみると、いずれの管理職などの割合においても10~29人規模の企業の女性管理職割合が最も高くなっています。中小企業だけでなく大企業においても女性管理職比率を高めていくことが課題の一つです。
女性管理職割合の推移に改善の兆しはみられるものの、たとえば、女性役員比率は日本を除くG7諸国の平均38.8%(2022年)に対し、日本は11.4%と低い水準にとどまっています。※※
政府は「女性版骨太の方針2023」において、プライム市場上場企業を対象とした女性役員比率に係る以下の数値目標を設定しました。
|
2024年12月25日の男女共同参画会議では、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業に対し「2025年までに女性役員比率19%」「女性役員がいない企業ゼロ」の中間目標が掲げられています。※※※
女性管理職比率 都道府県別(厚生労働省特別集計)
都道府県別に見ると、女性管理職比率には地域差が見られます。
厚生労働省の統計によると、2015年の都道府県別女性管理職比率は以下のとおりです。

大都市圏では大阪府や福岡県では全国平均を上回っていますが、東京都や愛知県などでは平均を下回っています。10%未満の県も多く、地域によって大きな格差があるのが現状です。
各自治体でも女性活躍推進に向けた施策が進められています。
女性管理職比率の国際的比較
国際的にみると、日本の女性管理職比率は低水準にあります。

管理職に占める女性の割合は、アメリカやフランス、北欧諸国では30%を超える水準が一般的です。これに対して日本は、15%以下にとどまり、東南アジアのフィリピンやシンガポールなどと比較してもきわめて低い水準となっています。
国際競争力を高めるうえでも、女性管理職登用の促進は急務といえます。
なぜ女性の管理職が少ないのか?社会的・組織的な背景と課題

女性管理職を増やすことが求められているものの、日本では女性管理職比率は依然として低い水準にあります。その背景にはどのような要因があるのでしょうか。
ここでは主要な要因について解説します。
働き続けにくい制度と家庭・育児の両立問題
日本では長時間労働を前提とした働き方が根強く、出産・育児などのライフイベントを迎えた女性がキャリアを継続することが難しい現状があります。
特に、管理職になるには柔軟な働き方では対応しにくい場面も多く、制度面のサポートが不十分な企業では、女性が昇進を諦めるケースも見られます。このような家庭と仕事の両立の難しさが、女性管理職の少なさにつながっているといえるでしょう。
ロールモデルの不在で管理職になりたがらない女性が多い
女性の管理職が少ない原因の一つがロールモデルの不在です。
HR総研のアンケートでは、企業が「女性活躍推進・女性登用に向けた課題」として挙げているのが、「女性ロールモデルの欠如」が最多で36%、ついで「女性の意識・就労観」が31%となっています。※
職場に女性管理職の先輩が少ない場合、若い世代の女性がキャリアパスを具体的にイメージできず、管理職への意欲を持ちにくくなるという問題が生じているのです。
ロールモデル不足でキャリアビジョンを描くことが難しく、「仕事と家庭を両立している管理職の女性がいない」「管理職になった後の働き方が想像できない」といった心理的なハードルが、管理職志向を低下させる要因となっています。
性別役割分担意識やバイアスがもたらす影響
日本社会の性別役割分担意識やバイアスも、女性管理職比率が伸び悩んでいる原因の一つに挙げられるでしょう。
帝国データバンクの統計では、「女性管理職の割合が上昇しない要因や課題」として「女性従業員の家庭と仕事の両立がしにくい」についで、「日本社会の性別役割分担意識の存在」「女性従業員が昇進を望まない」ことが挙げられました。※
女性管理職の仕事と家庭・育児の両立が難しいという要因は、制度的な問題もありますが、いまだに家庭・育児は女性がメインでおこなうもの、という性別役割分担意識が影響している側面もあります。
また、女性自身が昇進や管理職になるのを望まない点についても、ロールモデル不在や本人の意識だけでなく、パートナーや上司など周囲の無意識のバイアスや価値観が影響している点も見過ごせません。日本ではいまだ「管理職は男性向き」と考えるバイアスも根強く、これが女性登用を妨げる、隠れた障壁となっているのです。
管理職に向いてる女性の特徴とは?適性と必要なスキル

管理職に向いてる女性の特徴とは何でしょうか。
ここで注意したいのは「女性だから」という点でこだわって、管理職に必要な適性やスキルを考えることは、無意識のバイアスや性差別につながる危険があるということです。
女性であろうが男性であろうが、管理職に求められる役割や必要なスキルは変わらないはずです。「女性らしい細やかな気配りを」「女性だからこそ感情をコントロールして」といった表現や考え方は、性差バイアスや性差別につながりますから、経営層や人事部の方は特に注意するようにしましょう。
管理職に必要なスキル「ヒューマンスキル」「テクニカルスキル」「コンセプチュアルスキル」の3つのスキルについては、以下のコラムで詳しく解説していますので参考にしてください。
ここでは、冷静な判断力・チームマネジメント力・長期的視野という3つの観点から解説します。
冷静な判断力と感情コントロール
管理職には、部下からの相談や緊急事態への対応など、日々多様な判断が求められます。そのため、感情に流されず冷静に物事を見極める力が不可欠です。
感情を表に出しすぎると、部下が話しかけにくくなり、組織の円滑な運営に支障が出ることもあります。逆に、どのような状況でも落ち着いて対応できる姿勢は、部下に安心感と信頼を与えるでしょう。
仕事における感情コントロールやストレスマネジメントのやり方については以下のコラムを参考にしてください。
チームマネジメント力と信頼関係の構築力
管理職は、個人の成果だけでなく、チーム全体の成果に責任を持つ役割です。そのためには、メンバーの特性を理解し、それぞれに合った指導や支援ができるマネジメント力が求められます。
さらに、日々のコミュニケーションを通じて信頼関係を築く力も重要です。指示や注意を受け入れてもらうには、日常的な信頼の積み重ねが必要だからです。
相手の立場に配慮しながら接し、チーム全体をまとめる力のある女性は、管理職として大きな強みを発揮できます。
効果的なチームマネジメントの方法については、以下のコラムにあるチームビルディングの手法や具体例を参考にするとよいでしょう。
長期的視野で考えられる思考力・責任感
管理職には、目先の業務をこなしたり課題に対処したりするだけでなく、長期的な視点が必要です。たとえば、数年後の事業方針や人員構成を見越して業務を設計したり、部下の育成計画を立てたりと、将来を見据えて行動や計画する力が求められます。
同時に、その判断が会社全体に影響を及ぼすため、強い責任感も欠かせません。自分の役割の重みを理解し、先を見据えた行動ができる女性は、管理職としての資質に優れているといえるでしょう。
業務管理の方法やマネジメント能力が高い人の特徴などについては以下のコラムにまとめていますのでぜひご覧ください。
女性管理職を増やすための企業の取り組み

女性管理職を増やすためには、制度面と意識面の両方から環境整備を進めることが欠かせません。
最後に、女性管理職を増やすための具体的な取り組みについて、3つのポイントを解説します。
公平な評価制度と昇進機会の提供
女性が管理職を目指しやすい環境を整えるには、性別に左右されない公平な評価制度が不可欠です。
業績や成果を客観的に評価し、昇進のチャンスを均等に与えることで、女性社員のモチベーションを引き出せます。また、昇進基準を明確化し、誰もが納得できる仕組みを整えることで、女性自身がキャリアアップを現実的に描きやすくなります。
育児・介護と両立できる働き方の支援
出産や育児、介護など、ライフイベントと両立しながら働ける柔軟な制度設計も重要です。
たとえば、短時間勤務制度、フレックスタイム制度、在宅勤務制度などを活用することで、家庭と仕事を両立しやすくなるでしょう。
管理職ポジションでもこれらの制度を利用可能にすることで、時間的制約がある女性でもキャリア形成を諦めずに済む環境を実現できます。
ロールモデルの確立と継続的な教育投資
女性管理職を目指す上で、身近なロールモデルの存在は非常に大きな意味を持ちます。
成功している女性管理職の姿を見せることで、後進の女性社員たちに具体的な目標イメージを提供できます。
また、マネジメントスキルやリーダーシップを育成するための研修機会を積極的に設けることも効果的です。継続的な教育投資によって、女性社員のキャリア意識を高め、組織全体の多様性推進にもつながります。
【まとめ】女性管理職を増やすには

日本企業における女性管理職について現状と課題、求められる取り組みなどを解説しました。
日本は国際的にも女性管理職の割合が低く、政府は上場企業を中心に女性役員比率の目標を定めていますが、2025年度の中間目標達成も難しそうな状況です。
女性管理職比率が伸び悩んでいる背景には、育児や介護と両立しにくい制度にくわえて、女性自身が管理職になりたがらないという問題もあります。また、女性管理職比率の目標数値だけを追い求めて、むやみに女性管理職の数を増やせばよいというものでもありません。
女性管理職を増やしていくためには、制度的な面だけでなく、働く人自体の意識や企業の風土まで変えていく必要があるのです。
アイデンティティー・パートナーズは、企業と働く人々の課題解決を支援するため、研修や組織活性のコンサルティング、企業の研修内製化をサポートするコンテンツ開発などに取り組んでいます。
また、旧「日本女子経営大学院」を引き継ぎ、ダイバーシティ時代に対応できるリーダーを育てるアカデミア事業も展開しています。これらのサービスを支えるシンクタンクやサーベイ機能も備えており、企業全体を総合的に支援します。
女性活躍やダイバーシティ推進についてもさまざまなソリューションを提供しており、多くの導入事例がありますので、ぜひ一度ご参照ください。
▼導入事例のご紹介はこちら