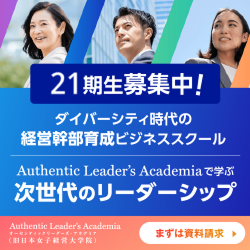管理職のコミュニケーションとして負担に感じるものは?
- なつき 高橋
- 2025年3月27日
- 読了時間: 6分

総研コラムでは、わたし・みらい・創造センター(企業教育総合研究所)(WMSC)の研究員らが「企業で働く個人のユニークネスと組織のオリジナリティを最大限に発揮する」ためのヒントとなるような知見や情報を提供します。近年、日本のビジネスにおいて、グローバル化やダイバーシティの推進など企業を取り巻く環境の変化が続いています。
また、リモートワークや居住地制限の緩和など、新たな働き方も進んでいます。そのような状況で、社内のコミュニケーションが重要な課題のひとつといえるでしょう。
そこで今回は、管理職のコミュニケーションについてお伝えします。
執筆者:川辺 晶弘
アイデンティティー・パートナーズ株式会社 わたし・みらい・創造センター(企業教育総合研究所) 研究員
【 目 次 】
上司として良いコミュニケーションではなかった…
「社内コミュニケーションに課題がある」とした企業が半数以上
管理職のコミュニケーションとして負担に感じるものは?
相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解する!
上司として良いコミュニケーションではなかった…

「心配なんてしても解決はしない。明日に備えて早く家に帰って寝なさい!」
これは約20年前、私がある部下に言った言葉です。
彼は翌日、あるトラブルを抱えたお客様である企業に行き、その対応をする予定でした。そして、その件について私に相談をしてきました。
「Aについてはどうだ? Bの準備は?」
私は、そのトラブル対応についての確認をしました。
彼は、必要な準備はすべて済ませていました。できる限りのことはやっていたのです。でも、彼は心配な様子でした。
「これでうまくいくかどうか…ダメだったらどうしましょう」
それで、私は冒頭の言葉を述べたのです。
いま思えば、上司として良いコミュニケーションであったとは思えません。
では、どうしたらよかったのでしょうか?
「社内コミュニケーションに課題がある」とした企業が半数以上

HR総研の「社内コミュニケーションに関するアンケート2024 結果報告」では、自社の社内コミュニケーションに関する課題についてどのように認識しているかを確認してみたところ、以下の結果となりました。
▼「課題」が「大いにあると思う」と「ややあると思う」の合計の割合
・従業員数1,001名以上の大企業では70%
・従業員数301~1,000名の中堅企業では67%
・従業員数300名以下の中小企業では60%
また、自社の社内コミュニケーション不全の原因の上位2つは、以下のものとなっています。
・「管理職のコミュニケーション力」
・「対面コミュニケーションの減少」
出典:HR総研「社内コミュニケーションに関するアンケート2024 結果報告」
この調査結果から、6割以上の企業が自社の社内コミュニケーションに課題があると認識していることがわかります。
そして、解決には、「管理職のコミュニケーション力」と「対面コミュニケーション」が重要なものであることもわかります。
管理職のコミュニケーションとして負担に感じるものは?
では、管理職として対面でコミュニケーションをする際に、どのようなことが問題なのでしょうか?
ポルムス株式会社の「管理職の負担」に関する調査」(2024年9月)によると、管理職に対して「社員から悩みを相談される機会はありますか?」と質問したところ、以下の結果となりました。
・とてもある 16.8%
・ややある 52.3%
・あまりない 25.4%
・全くない 5.5%

そして、社員から悩みを相談されたときに、「とても負担を感じる」「やや負担を感じる」と回答した管理職に「どのような点に負担を感じますか?(上位3つまで)」と質問したところ、上位2つは以下の内容のものでした。
・適切なアドバイスをすること 44.4%
・部下の感情を受け止めること 32.8%
出典:ポルムス株式会社「管理職の負担に関する調査(2024年9月)」
つまり、約7割の管理職が悩みを相談されていることになります。
そして、相談に負担を感じる管理職の重要課題は、「適切なアドバイスをすること」と「感情を受け止めること」といえるでしょう。
相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解する

冒頭に書いた20年前の私の発言。
「心配なんてしても解決はしない」
部下の感情を受け止めるという視点ではどうでしょうか?
感情を受け止めるばかりか、突き放しています。目も当てられません。恥ずかしい…。
「明日に備えて早く家に帰って寝なさい!」
これも適切なアドバイスという視点ではどうでしょうか? 最悪ではありませんが、かなり微妙です。
では、上司のコミュニケーションの課題を達成するには、どうしたらいいのでしょうか?
私たち総研では、「臨床心理学をビジネスに応用する」という研究も行っています。
臨床心理学の分野に、心理カウンセリングの理論とスキルもあります。
心理カウンセリングでは、カウンセラーが傾聴しながら相談者の話を聴きます。
傾聴とは、相手の話を、相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとすることです。
つまり、話の内容だけではなく、感情も理解しようとする試みです。むしろ、後者のほうを重要視しています。
また、カウンセラー側から伝える応答やコメントには、YOUメッセージとIメッセージの使い分けを行うこともあります。
・YOUメッセージ:相手のこと自体についてコメントすること
・Iメッセージ:自分のこと自体についてコメントすること
このような理論とスキルは、専門家として身に着けるものです。
ただ、その重要なポイントを簡潔にして、ビジネスの世界で活用することは難しいことではありません。
これらのものを習得することは、管理職のコミュニケーション能力の向上に大いに役立つものとなるでしょう。
実際に、そのような研修やトレーニングを導入している企業も多くあります。
「心配なんだな。それは当然だよ。でも、あなたは用意周到で、やるべきことはやったよ。頼りになるよ。明日は、まず○○をチェックして。それで対策が決まるから。そして、何か困ったことがあったらすぐに連絡しなさい」
当時の私も、こんなふうに言える能力を身につけていたら、もう少し彼の心配を軽減できていたでしょう。
時は流れ、実はいまでも彼とは連絡を取り合っています。社内コミュニケーション不全の原因に「対面コミュニケーション」と「飲み会」の減少がありますが、逆にこれらの機会が多かったことが幸いしたのかもしれません。
そして、当時以上に、いまの管理者には、より質の高いコミュニケーション力が求められているといえるでしょう。
そのためにも、私たちは、心理学の知見を組織のコミュニケーションに活かす研究を進めていきたいと思っています。
▼この記事を書いた人
川辺 晶弘(かわべ まさひろ)
〈プロフィール〉
ソフトウェア・システム会社にて、新規事業の立ち上げ、法人向けシステムの導入・指導・営業に携わる。
社内では新入社員や部下の教育・指導・相談業務を行う。
その後、教育研修会社にて、メンタルヘルス・臨床医学(心理療法・カウンセリング)・コミュニケーション・コーチングに関する研修の企画・開発・講師を務める。
また、職場のメンタルヘルス支援や心理カウンセリングにも携わる。
その間、国内外の一流心理療法家から、心理療法の理論・技法、グループアプローチなどを学ぶ。
アイデンティティー・パートナーズ株式会社では、「わたし・みらい・創造センター」にて研究・開発業務に従事している。