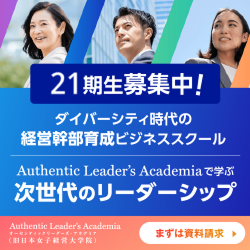「今、人と組織が競争する働き方の未来へ」 第20回エグゼクティブメンターイベント実施レポート
- saganmm
- 2月18日
- 読了時間: 8分
オーセンティックリーダーズアカデミアは12月7日、第20回エグゼクティブメンターイベントをオンラインで開催した。約120名が参加したこのイベントでは、「今、人と組織が競争する働き方の未来へ」をテーマに、働き方改革から働きがい改革への転換について、第一線で活躍する経営者や実務家らが議論を展開した。

2015年の日本女子経営大学院としての開学以来、働き方改革や女性活躍を中心に展開してきた同アカデミアは、2019年からSDGs・人的資本経営・DEIなど、より幅広いテーマを扱うように進化。2024年からはアイデンティティパートナーズとの統合により、より広範な人材開発・組織開発のソリューションを提供する第3フェーズに入る。
アカデミアの変革と新たな挑戦
冒頭、同アカデミア学長の河北隆子氏が開会の挨拶を行った。河北氏は、2015年1月の開学から現在までの軌跡を振り返りながら、スクールの変革について語った。
「私どもは2015年の開学以来、社会の喫緊の課題をテーマとして、一億総活躍社会を実現すべく、働き方改革、女性活躍を含むダイバーシティ推進などのソリューションとして歩んでまいりました」と河北氏は説明。「現在は第3フェーズを迎え、2024年11月にはアイデンティティパートナーズ株式会社として統合し、より領域を広げ、より創造的に、多様なチームメンバーとともに、立ち来るオーセンティックなリーダーを養成していく」と、新たな展開への意欲を示した。
同スクールの実績について、受講者数は1,010名、派遣企業数は145社に達している。「多様な業種業界の枠を越えて集い、ビジネスを通じて社会的価値創造を学ぶ場であり、未来をつくる自分を育てるビジネスパーソンのためのスクール」と河北氏は位置づけた。

第一部:基調講演 「今改めて問われる働きがいの改革」
Great Place to Work Institute Japan代表の荒川陽子氏による基調講演では、働きがいのある会社作りの具体的な方法論が示された。
コロナ禍での経営改革
2020年にGPTW代表に就任した荒川氏は、コロナ禍での就任について「逆にラッキーだと思いました。業績が出なかったとしても『コロナですから』と言える。これが非常に好調な市場の中で自分が社長になって業績が上がらなかったら大変です」と、危機をチャンスに変えた経験を共有。「変化に対応することと、ヘルシーに働くという方針を打ち出し、社長就任前の1年間で温めていたことを次々と具体化していきました」と語った。
働きがいの定義と日本企業の課題
荒川氏は、働きがいのある会社の定義について「働きやすさとやりがい、この両方が備わっている組織である」と説明。特に日本企業の課題として、グローバル比較における「誇り」の低さを指摘した。
「日本において働きがいが高いと言われている企業であっても、アジアのランキングだったり、アメリカのランキングやヨーロッパのランキングに比べると、前設問平均や誇りのスコアが全然違う。特に誇りに差があることが見ていただけると思います」と分析を示した。
働きがいを高める具体的施策
具体的な成功事例として、ブラックライン社の取り組みが紹介された。「顧客の感謝の声やコアバリューを共有する、社内SNSで感謝の言葉を閲覧できるようにする、全社ミーティングでランダムに感謝する人を90秒で褒める」など、具体的な施策が共有された。
また、リグリットパートナーズの事例では、「サービスポリシーとして独自の差別化したコンサルティングスタイルを設定し、その共感と体現を求める」という approach が紹介された。月600名の中途入社希望者から2%という厳選な採用を行い、同じ方向を向いて仕事をする組織作りを実現している。

第二部:パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、ベルシステム24ホールディングス常勤監査役の浜口聡子氏、ホクト株式会社人事部部長の西澤賢氏、NTTデータ第4公共事業本部デジタルコミュニティ事業部部長の浜口麻里氏が登壇し、それぞれの立場から組織変革への取り組みを語った。
共感型経営の重要性
浜口聡子氏は、36年間の同社でのキャリアを振り返りながら、経営者に必要な資質について語った。「不透明な時代で、なかなか成長戦略も描きにくい中で、この会社をどうしていきたいとか、何を成し遂げたいという経営者の夢が、しっかりと従業員に言語化して語られることが重要です。そこに求心力が回る。社長の思いにどれだけ社員が共感できるか、共感型の経営が今後は必要」と指摘した。
イノベーションを生み出す組織作り
北斗の西澤氏は、研究職から人事部長への異色のキャリアを持つ。「きのこの研究から人事という未知の分野に移った時、分からないものは聞いて覚えるしかない。周囲の人たちは全員先生というマインドで学びました」と、キャリアチェンジの経験を語った。
多世代マネジメントについては、「年齢とか世代で育ってきた環境は違うので、今だと仮に上の立場とか年が上だとしても、下の人たちが今大事にしていることを探求していかないといけない」と、双方向のコミュニケーションの重要性を強調した。
経営層としての視野の広がり
NTTデータの浜口麻里氏は、2022年の産休育休を経て、部長として復職した経験を持つ。部長昇進後の変化について「カウンターパートが変わることで、お客様の悩み事も違ってきます。目の前のシステム化という課題から、より大きな社会課題にアクセスできるようになった」と、視野の広がりについて語った。
質疑応答から見える現場の課題
パネルディスカッション後の質疑応答では、参加者から「望まないキャリアでも前向きに捉えて成長の糧とされていることが印象的です。若手社員は配属ガチャで望まない部署になった時のモチベーションダウンが激しいのですが、自ら前向きになれるようにするには、どんなアドバイスをされますか?」という質問が寄せられた。
これに対して西澤氏は、「仕事に対する捉え方の違い」について興味深い指摘を行った。「後輩と話して気づいたんですが、仕事は楽しいものだと捉えている人と、私のように仕事は苦しいものだと思っている人がいる。私は苦しいからこそ努力しなきゃ楽にならないと思っているんですが、その人は楽しいから自分で進められる。全く違う考え方なんです」

参加者の声から見る学びの成果
本音で語り合える場としての意義
「普段は社内では共有しづらい悩みや課題について、率直な対話ができる貴重な機会でした。それぞれの立場で直面している課題を共有し合うことで、新たな視座を得ることができました。このイベントを通じて、自分らしいリーダーシップの在り方を改めて考えるきっかけとなりました」
マネジメントの実践知
「人材開発部門の責任者として日々奮闘していますが、GPTWの荒川さんが提示された『働きがいと働きやすさの融合』という考え方は、組織変革の新たな切り口となりました。特に感謝の可視化など、具体的なアクションにつながる示唆を得られました」
「日本企業における『誇り』の醸成という視点は、まさに目から鱗でした。早速、お客様からの声を組織内で共有する仕組みづくりに着手しています」
リーダーシップの新たな視点
「部長就任後、組織をどう導いていくべきか模索していました。浜口さんの『経営ビジョンの言語化と共感づくり』という観点は、自分のリーダーシップスタイルを考える上で重要な示唆となりました」
「世代間の価値観の違いについての議論は、若手との対話に新たな視点をもたらしてくれました。特に『仕事観の多様性』への理解は、日々のマネジメントに活かせる学びでした」
実践的な課題解決の場
「配属や異動に関する部下とのコミュニケーションに悩んでいましたが、パネリストの経験談から具体的なアプローチのヒントを得ることができました」「登壇者の皆さんが、成功体験だけでなく、実際の困難やその克服プロセスを共有してくださったことで、自組織での実践に向けた具体的な示唆を得られました」
イノベーティブ経営人材育成への新たな取り組み
イベント後半では、2024年1月から開講される「イノベーティブ経営人材育成コース」の説明が行われた。このコースは、部長職または同等クラスを対象とした、総合的・横断的に学べる経営幹部育成のプログラムとして設計されている。
カリキュラムは、経営戦略実践、アート思考とイノベーション、マインドフルネスなど、多彩な内容で構成。特徴的なのは、アクションラーニングセッションにおいて、受講者1名につき同行者1名が参加できる仕組みだ。これにより、学びを組織に展開しやすい環境が整えられている。

新しい時代の経営課題に向けて
イベントを通じて浮かび上がってきたのは、単なる制度や仕組みの改革を超えた、「働きがい」を軸とした新しい組織づくりの重要性である。荒川氏が指摘した「働きやすさとやりがいの両立」、浜口聡子氏が述べた「共感型経営」、そして現場からの変革を重視する西澤氏の視点は、まさに現代の組織が直面する課題に対する示唆に富むものであった。
西澤氏の「物事は大きくすぐには変えられないが、変えていこうとしていることを社員に分かってもらう。それがないと閉塞感が広がる」という言葉は、組織変革に取り組む多くの経営者、管理職の心に響くものだろう。
イベントは、経営人材育成の新たな展開を予感させる充実した内容となり、参加者それぞれが自組織での実践に向けた多くの示唆を得る機会となった。